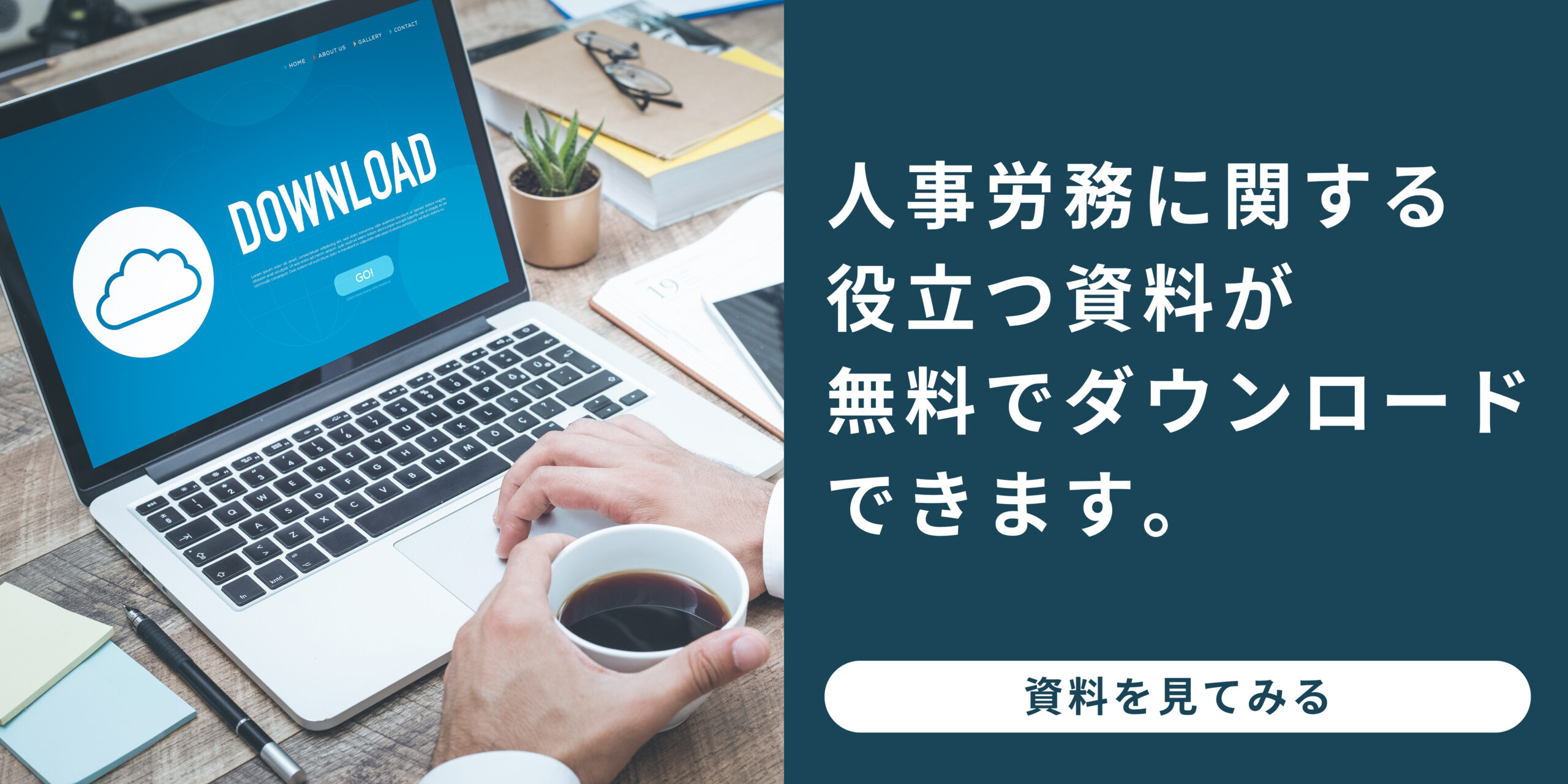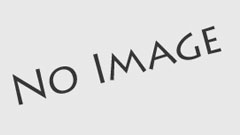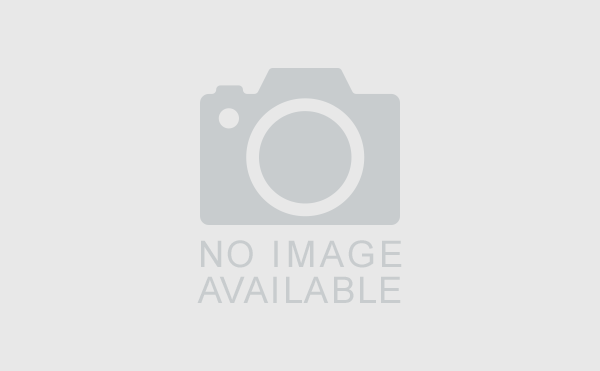第6回:「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (3) ― 規程と等級決定
1.はじめに
前回は、会社にある様々な仕事を洗い出し、カードに書き出して整理する「仕事しらべ」という作業を行いました。会社の仕事という「森」を、一つ一つの「木」として捉え直し、その木の高さ(難易度や責任)によって分類する、地道ですが非常に大切な作業でした。
「うちにはそんなに多くの仕事はないよ」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、経営管理の仕事、社員を教育する仕事、職場を良くするための活動など、普段は意識しないけれど、会社の存続・発展には欠かせない仕事がたくさんあるはずです。そうした隠れた仕事も含めて掘り起こし、その難易度によって「等級」に分類していきました。これが、社員一人ひとりの成長段階を示す「資格等級制度」の基礎となる作業でした。
今回は、この「資格等級制度」をさらに具体的に設計していくフェーズに入ります。具体的には、この制度の「ルールブック」となる資格等級規程を作成し、各等級で求められる能力レベルを明確にする資格等級定義表を完成させ、それらに基づいて社員一人ひとりを今の等級に位置づけ(等級決定)、そして社員が上の等級に上がるための「道筋(昇格条件)」を定めます。
これまでの作業で、なんとなく「うちの社員には、これくらいのレベルの仕事ができるようになってほしいな」「このくらいの責任を担えるようになれば、次のステップだな」といったイメージをお持ちになったかもしれません。今回の作業は、そのイメージを具体的な「制度」として形にする作業です。単に社員をランク付けするのではなく、社員自身が「次に何を頑張ればいいのか」「会社は自分に何を期待しているのか」を明確に理解し、自らの成長に向けて意欲的に取り組めるようにするための、非常に重要なステップなのです。
2.資格等級規程の作成:なぜ「ルールブック」が必要なのか?
皆さんの会社では、昇給や昇格、異動といった人事に関する決定を、社長であるあなたが感覚的に、あるいは「まあ、これでいいだろう」という判断で行っている部分があるかもしれません。特に社員数が少ないうちは、社長が個々の社員のことをよく分かっているので、それでも回ってしまうかもしれません。
しかし、会社が成長し、社員が増えてくると、そうした属人的な判断では難しくなってきます。社員から見れば「社長の気分で決まっているのでは?」「どうしてあの人が昇給・昇格したんだろう?」といった疑問や不満が生まれる可能性があります。また、社長一人で全ての判断をするのは、社長自身の負担も大きくなります。
そこで必要になるのが、「人事に関するルールブック」です。資格等級制度におけるルールブック、それが「資格等級規程」です。
規程というと、なんだか難しそうに聞こえるかもしれませんが、要は「この制度は、何のために、どんな仕組みで、どのように運用するのか」を、社員みんなが理解できるように、そして将来にわたってぶれないように、きちんと書き記しておくものです。
この規程に定めるべき主な項目は、例えば次のようなものです。
- 目的:この資格等級制度は何のために作るのかを明記します。単に給与を決めるためだけではなく、社員の能力開発を促進し、成長を支援するため、そして会社全体として必要な能力を高めていくためといった、「人を育てる」という本制度の根幹にある目的をしっかりと打ち出します。
- 資格等級の種類:自社が採用する等級数を定めます。一般的には6等級または8等級が適切とされています。前回までの「仕事しらべ」で、自社の仕事の難易度や責任の段階が何段階くらいに分けられそうかが見えてきたはずです。その結果を基に、自社に合った等級数を決めましょう。また、社長や専務、常務といった経営層は等級の対象外とするのが一般的ですが、取締役〇〇部長といった役割を持つ方は等級に入れる、あるいは特定の専門性を持つ社員のために「専門職」というコースを設けるなど、自社の実情に合わせて定義します。
- 資格等級の格付け:社員を各等級に位置づける際の基本的な考え方を定めます。重要なのは、資格等級は「社員の能力」によって決定されるということであり、役職は「組織の必要性」によって決まるということです。つまり、「部長だから〇等級」と固定するのではなく、あくまでその社員の能力レベルで等級を決めるという考え方です。もちろん、特定の役職には「〇等級以上の能力が求められる」といった目安は設定しますが、能力と役職は必ずしも一致しない、という柔軟性を持たせることが、社員の能力を正当に評価し、成長を促す上で大切になります。
- 初任格付け:新しく社員になった人が、最初どの等級からスタートするのかを明確に定めます。新卒採用の社員は、通常は一番下の等級(例えば1級)からスタートとします。大学卒や大学院卒といった、より基礎的な知識を身につけている社員に対しては、早期に次の等級(例えばⅡ級)に昇格できるような制度を設けることも有効です。
- 中途採用者:中途で入社する社員の最初の等級決定方法も定めます。中途採用者の格付けは、その人の年齢やこれまでの経験、能力を考慮して行いますが、具体的な判断材料として、前回行った「仕事しらべ」で整理した仕事内容を参照します。また、規程で「中途入社社員の格付けについてはその都度決める」とすることもできますが、一定の基準があった方が公平性は高まります。現場では、中途採用者は予定している等級の「一つ下の等級」で設定し、周りの社員の評価が固まる1年後くらいに予定の等級に上げるのが良い、という意見もあります。これは、入社前に把握できなかった情報や、入社後の実際のパフォーマンスを見極める期間を設けるという意味合いで有効な考え方です。
- 昇格:社員が上の等級に上がるための条件やプロセスを定めます。これについては後ほど詳しく触れますが、規程に定めておくことで、社員は「何を、どれくらい頑張れば上の等級に上がれるのか」という明確な目標を持つことができます。
こうした項目を規程として定めることで、資格等級制度は単なる社長の頭の中のイメージではなく、社員みんなが共有できる、明確な「会社のルール」となります。これは、制度の公平性・透明性を高め、社員からの信頼を得る上で非常に重要です。
3.資格等級定義表の作成:等級ごとの「能力レベル」を具体的に描く
資格等級規程が制度の「骨組み」だとすれば、「資格等級定義表」は、その骨組みに肉付けをし、「各等級でどのような能力や役割が期待されるのか」を具体的に記述したものです。
前回の「仕事しらべ」では、会社にある様々な仕事を難易度で等級に分類しました。この定義表は、その等級分類の根拠となる「等級ごとの能力レベル」を言葉で表現するものです。例えば、1級の社員にはこのレベルの仕事が、2級の社員にはこのレベルの仕事が期待される、といった具合です。
定義表を作成する目的は、主に二つあります。
一つは、社員が自分のいる等級で何を期待されているのか、そして次の等級に上がるためにはどのような能力を身につける必要があるのかを明確に理解できるようにするためです。これは、社員が自らのキャリアパスを描き、目標を設定する上で非常に重要な「道しるべ」となります。
もう一つは、等級決定や昇格判断の際の基準として活用するためです。前回「仕事しらべ」で分類した仕事が、どの等級に該当するのかを判断する際に、この定義表に書かれた能力レベルを参照します。例えば、「トラブル発生時に一人で対応できる」という仕事は3級レベルだ、と定義表に書かれていれば、「トラブル対応能力」は3級に求められる能力レベルの一つだということが分かります。
定義表に記述する内容は、等級が上がるにつれて、より難易度の高い仕事、より広い範囲への影響力、より高い責任、より高度な知識・スキル、そして部下指導や管理といったマネジメント能力などが求められる、というように段階的に変化させていきます。
例えば、6等級の会社であれば:
- 1級(一般・初級):定型業務ができる、上司の指示に従って正確に作業できる、といったレベル。
- 2級(一般・上級):定型業務を一人で完遂できる、ある程度のトラブル処理ができる、経験と知識が十分にある、といったレベル。
- 3級(指導職):業務に精通しており、部下の指導・育成ができる、といったリーダー的な役割が期待されるレベル。
- 4級(初級管理職):係を統括する、といった係長クラスの管理職レベル。
- 5級(中級管理職):課を統括する、といった課長クラスの管理職レベル。
- 6級(上級管理職):部を統括する、といった部長クラスの管理職レベル。
(※上記はあくまで例であり、自社の組織や実情に合わせて定義します。)
定義表の作成作業は、社長であるあなた(またはプロジェクトリーダー)が中心となって案を作成し、プロジェクトメンバーや他の管理職に見てもらいながら進めるのが良いでしょう。様々な立場の人に確認してもらうことで、実態に合った、そして皆が納得できる定義に近づけることができます。
この定義表は、一度作ったら終わりではありません。会社の事業内容が変わったり、社員に求める能力レベルが変わったりすれば、見直しが必要です。常に「今の会社にとって、この等級の社員にはどのような能力や役割を期待するのか」を問い直し、実態に合わせて更新していくことが大切です。
4.社員の資格等級決定:一人ひとりを成長の道に位置づける
資格等級規程と資格等級定義表が完成したら、いよいよ現実に社員一人ひとりを、どの等級に位置づけるのか(現等級の決定)という作業を行います。
これは、「会社は、あなたの今の能力レベルをこのように見ていますよ」というメッセージを伝える、非常に重要な機会となります。そして同時に、「あなたには、今後〇等級、△等級とステップアップしていくことを期待していますよ」という、成長への期待を伝えることにもなります。
等級決定は、単にこれまでの年功序列や社長の感覚で行うのではなく、作成した規程と定義表を基準に行います。具体的な判断材料としては、主に以下の点を考慮します。
- 現在の仕事内容と能力:前回までの「仕事しらべ」で整理した、その社員が現在担当している仕事の内容と、それを遂行するために必要な能力。定義表に照らし合わせて、その仕事や能力がどの等級レベルに該当するかを判断します。
- これまでの経験や実績:入社からの年数、これまでの様々な業務経験、過去のプロジェクトでの役割、そして目に見える実績などが判断材料となります。
- 規程で定めた基準:新卒は1級から、中途採用者は年齢や能力、そして仕事しらべの内容を参照して決定するといった、規程で定めた初期格付けの考え方に基づいて判断します。
社員の等級を決定する際は、プロジェクトメンバーや直属の上司の意見も聞きながら、総合的に判断することが大切です。特に、その社員の能力を最も近くで見ている直属の上司の意見は重要です。
等級決定の結果は、社員本人にきちんと伝える必要があります。その際、「なぜその等級になったのか」という根拠や、会社がその等級の社員に何を期待しているのか、そして今後どのような成長を期待しているのかを丁寧に説明することが、社員の納得感とモチベーションに繋がります。単なる「あなたは〇級です」という一方的な通知ではなく、会社と社員が一緒に成長のステップを確認する機会と捉えましょう。
中途採用者を予定等級の一つ下でスタートさせる場合は、その意図(期待する能力を発揮できれば〇年後には予定等級へ、といったステップ)をしっかり伝えることで、本人の安心とモチベーションに繋がります。
5.昇格条件:成長への「道筋」を照らす
資格等級制度は、社員の現在の能力レベルを示すだけでなく、社員がより上位の等級を目指し、成長していくための制度です。そのためには、「どうすれば上の等級に上がれるのか」という「昇格条件」を明確に定めることが不可欠です。
昇格条件が曖昧だと、社員は何を頑張ればいいのか分からず、成長の目標を見失いがちになります。逆に、昇格条件が明確であれば、社員はそれを目標に日々の業務や自己啓発に取り組むことができます。これは、社員の自律的な成長意欲を引き出し、会社全体の能力向上に繋がる非常に強力な仕掛けとなります。
昇格は、「この社員は、次の等級で求められる能力や役割を担う準備ができた」と会社が認めるプロセスです。規程や定義表に基づいて、昇格の際にどのような点を評価・判断するのかを具体的に定めましょう。
- 過去の定期評価の結果:単に直近の評価だけでなく、過去数年間(例えば2年間や3年間)の評価結果を総合的に判断します。これは、一時的な頑張りだけでなく、継続的な努力や成果が重要であることを示すメッセージとなります。毎日の業務で求められる能力発揮や勤務態度、そして設定した目標に対する取り組みといった、日々の積み重ねが昇格に繋がることを社員に理解してもらいましょう。行動評価制度による評価は、単に社員の優劣をつけるためではなく、一人ひとりの能力や行動の「良い点」と「課題」を明確にし、それを成長に繋げることを目的としています。この評価結果が昇格の重要な判断材料になることを示すことで、社員は日々の評価を真剣に受け止め、改善に取り組むモチベーションが高まります。
- キージョブ遂行能力の有無:これは非常に重要な要素です。前回の「仕事しらべ」で、各等級の「最も重要な仕事」としてキージョブを3~4個決定しましたね。昇格条件として、「昇格後の等級で求められるキージョブを遂行できる能力があるか」を判断基準とします。例えば、2級に昇格するためには、2級のキージョブである「ある程度のトラブル処理」が一人でできる必要がある、といった具合です。社員は、自分が目指す等級のキージョブを知ることで、「あの仕事ができるようになれば昇格できるんだな」という具体的な目標を持つことができます。
- 昇格試験の結果(規定の通信教育など):等級によっては、特定の知識やスキルを体系的に習得していることを昇格の条件とする場合があります。例えば、1級から2級への昇格条件として、会社が指定する通信教育の選択科目を一つ以上終了していること、といった具合です。これは、実務経験だけでなく、自己啓発による計画的な能力開発も評価対象とするというメッセージになります。能力開発制度との連携を示すことで、社員は自己投資の重要性を認識するでしょう。
- 面接結果、論文試験結果:上位等級への昇格においては、筆記試験や面接を行うこともあります。これは、単なる業務遂行能力だけでなく、より広い視野や問題解決能力、リーダーシップといった、上位等級に求められる能力を総合的に判断するためです。
- 最低在籍年数:一つの等級に一定期間在籍していることを昇格条件に加える場合もあります。これは、ある程度の経験を積むことも重要であるという考え方に基づきます。ただし、これはあくまで目安とし、能力や実績が著しい社員については、在籍年数に関わらず昇格を検討する、といった柔軟性も必要でしょう。
昇格の方法としては、「人事評価の結果に加えて試験を行う試験昇格」と、「人事評価の結果のみで昇格する一般昇格」の二つを定めることができます。どの等級への昇格時に試験を課すかなど、自社の実情に合わせて検討します。
これらの昇格条件を明確に定めることで、社員は「頑張れば報われる」という感覚を持ちやすくなります。ただし、条件設定には注意が必要です。あまりに厳しすぎると、社員は「どうせ無理だ」と諦めてしまい、モチベーションが下がってしまいます。逆に緩すぎると、制度の形骸化を招き、社員の成長意欲を刺激できません。「頑張れば手が届く、でも簡単ではない」という、絶妙なバランスの条件設定を目指しましょう。
また、規程には「特殊な事情がある場合には、この基準を外れても特別に昇格を認めたり、昇格を遅らせたりすることがある」といった条項を設けることも考えられます。これは、制度を杓子定規に運用するのではなく、個別の事情に配慮するための柔軟性を確保するためですが、乱用は制度の公平性を損なうため避けるべきです。
昇格条件を社員に伝える際は、単に「〇〇ができれば昇格できます」と伝えるだけでなく、「なぜその条件が必要なのか」「それをクリアすることで、あなたにどのような成長が期待できるのか」といった、制度の背景にある考え方を丁寧に説明することが大切です。
6.資格等級制度運用の心構え:成長の「道しるべ」として活用する
今回、資格等級規程、定義表、そして社員の等級決定と昇格条件についてお話ししました。これらはすべて、「社員を育てる」というこの人事制度の大きな目的を達成するための重要な要素です。
資格等級制度は、単に社員を「ランク付け」して、給与や役職を決めるためだけのツールではありません。それは、社員一人ひとりの「現在の能力と会社の期待」を示すと共に、「次に目指すべき姿」を具体的に指し示す、「成長の道しるべ」なのです。
この「道しるべ」があるからこそ、社員は「今の自分はここだけど、次は〇等級を目指そう」「そのためには、△△のキージョブができるようにならなきゃ」「評価で指摘された課題を克服するために、□□の通信教育を受けてみよう」といった具体的な目標を持ち、自律的に成長しようという意欲を持つことができます。そして、社員が成長することは、会社の成長に直結します。
資格等級と役職を固定的に連結しないことは、この「成長の道しるべ」としての機能を高めます。役職ポストが限られていても、能力を伸ばせば等級が上がることで、社員は自身の成長を実感し、認められているという感覚を持つことができます。これは、社員の「働きがい」を高める上でも非常に重要です。
この資格等級制度を効果的に運用するためには、いくつかの心構えが必要です。
- 社員への丁寧な説明:なぜこの制度が必要なのか、各等級で何を期待しているのか、どうすれば昇格できるのか、といった制度の意義や仕組みを、社員一人ひとりに分かりやすく伝えることが不可欠です。社員が制度を理解し、納得していることが、前向きな運用の第一歩です。
- 評価者(管理職)の理解と訓練:この制度は、特に管理職が部下の能力や成長を正しく理解し、指導する上で重要なツールとなります。管理職自身が制度の目的や等級定義、昇格条件を深く理解し、部下との面談でそれを活用できるように、十分な訓練を行う必要があります。実は、人事制度を運用することで一番能力が向上するのは、「評価される人」よりも「評価する人」、つまり管理職自身なのです。
- 柔軟な運用と見直し:一度作った規程や定義表も、会社の変化や社員の状況に合わせて柔軟に見直す姿勢が大切です。完璧な制度を最初から目指すのではなく、「60点でもいいから、まずは導入してみる」という「60点・導入主義」の精神でスタートし、運用しながら改善していくのが中小企業には現実的です。
社長であるあなたが、この資格等級制度の「人を育てる」という本質を誰よりも理解し、社員にその思いを伝え、制度運用をリードしていくことが、この制度を成功させる上で最も重要です。社員は社長の姿勢をよく見ています。「社長が本気で社員の成長を願っているんだな」ということが伝われば、社員もきっとそれに応えてくれるはずです。
7.まとめ
今回は、資格等級制度の具体的な設計として、制度の根幹をなす資格等級規程、各等級の能力レベルを示す定義表、そして社員一人ひとりの等級決定方法と、成長への道筋となる昇格条件について掘り下げてお話ししました。
これらの要素は、単に社員を管理するためのものではありません。社員が自分の能力を会社に認められ、成長の目標を持ち、それに挑戦し、そして評価されることで、さらに意欲を高める。そんな「成長の循環」を生み出すための、大切な仕掛けなのです。そして、社員一人ひとりの成長が、会社の持続的な発展に繋がっていくのです。
次回は、この資格等級制度と連携して、社員の頑張りや能力発揮を適切に評価するための「人事評価制度」について、特に「行動評価」の具体的な仕組みについてお話しする予定です。
今回もお読みいただき、ありがとうございました。共に、社員が輝き、会社が発展する人事制度を創り上げていきましょう!
投稿者プロフィール

-
木戸社会保険労務士事務所の三代目の石田厳志と申します。当事務所は、私の祖父の初代所長木戸琢磨が昭和44年に開業し、長年に渡って企業の発展と、そしてそこで働く従業員の方々の福祉の向上を目指し、多くの皆様に支えられて社会保険労務士業を行ってまいりました。
当事務所は『労働保険・社会保険の手続』『給与計算』『就業規則の作成・労働トラブルの相談』『役所の調査への対応』『障害年金の請求』等を主たる業務としており、経営者の困り事を解決するために、日々尽力しています。経営者の方々の身近で頼れる相談相手をモットーに、きめ細かくお客様目線で真摯に対応させていただきます。
最新の投稿