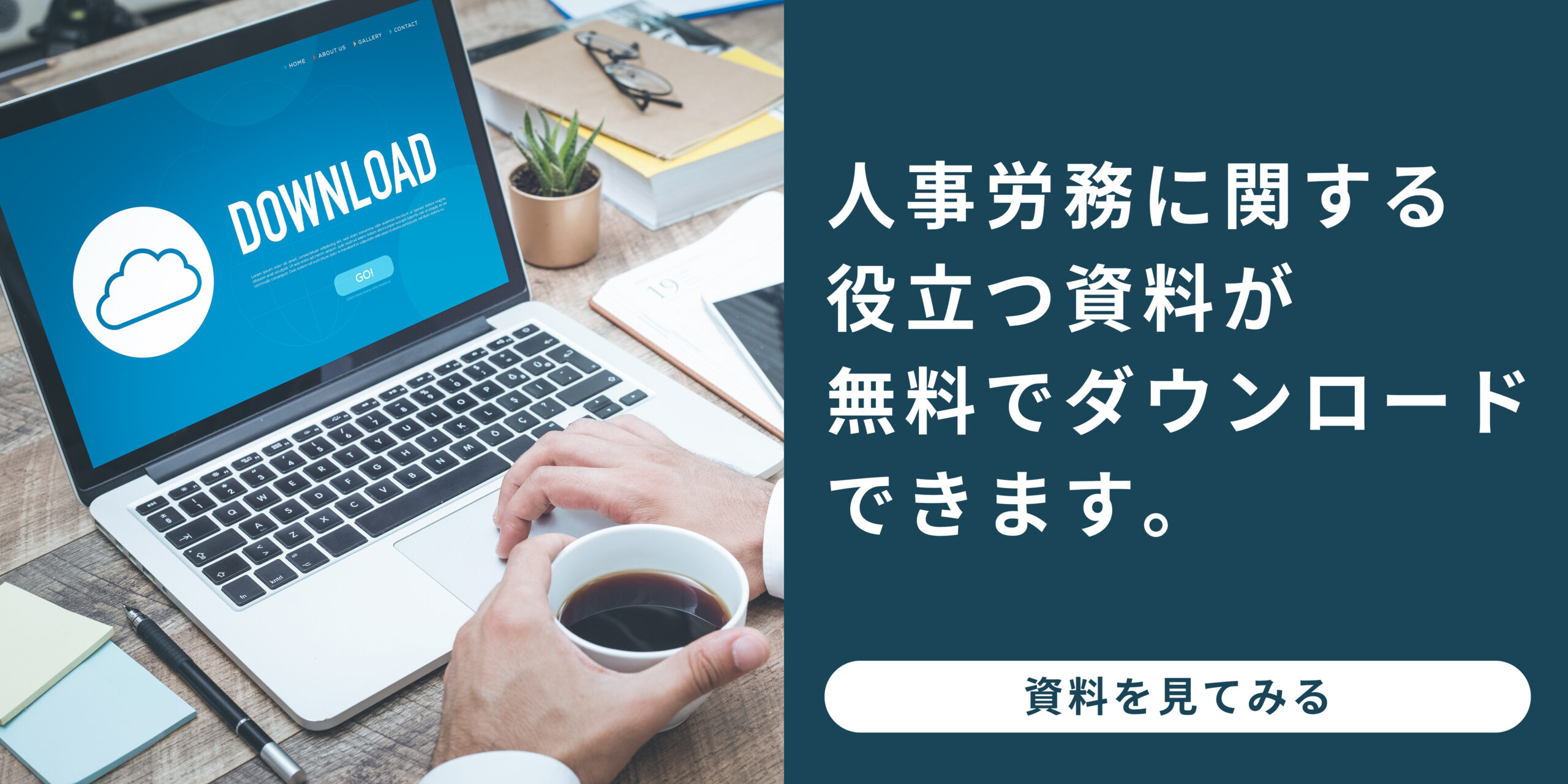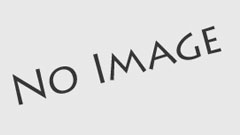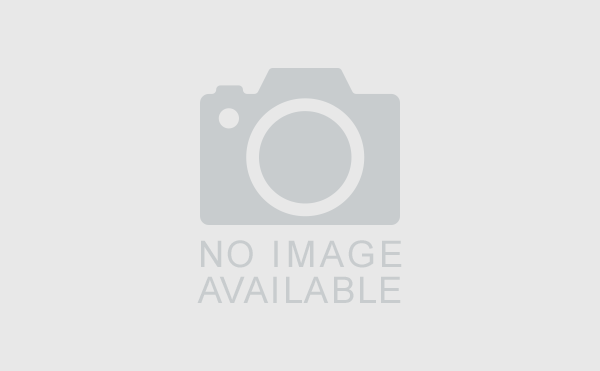第3回:「人を育てる人事制度」フレームワーク作業
1.はじめに
前回は、貴社独自の人事制度を作るためのプロジェクトチームを立ち上げ、その第一歩となるキックオフミーティングを開催しました。いよいよ、「人を育てる人事制度」策定に向けた本格的な活動が始まるわけですが、今回はその中でも非常に大切なステップである「フレームワーク作業」について、詳しくお話ししたいと思います。
2.なぜ、フレームワーク作業が必要なのか?
中小企業の経営者の皆さんにとって、日々の業務は多岐にわたり、まさに目が回るような忙しさだと思います。そんな中で、「人事制度を新しく作るぞ!」とプロジェクトを立ち上げたものの、「一体何から手をつければいいんだ?」「どんな制度を目指せばいいんだ?」と、漠然とした不安や疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。プロジェクトメンバーの皆さんも、同じような気持ちかもしれませんね。
そこで登場するのが、「フレームワーク作業」です。この作業は、言ってみれば、これから始まる人事制度策定プロジェクトの「羅針盤」を作るようなものです。船が大海原に出る前に、目的地を明確にし、航路を定めるように、プロジェクトメンバー全員で「何の目的で、何を対象に、どこまでおこなうのか」を徹底的に話し合い、明確にする作業なのです。
この目的や方向性が曖昧なまま制度設計を進めてしまうと、途中で議論がブレたり、最悪の場合、完成した制度が「ウチの会社には合わないな」「なんかピンとこないな」ということになりかねません。これでは、せっかく時間と労力をかけたプロジェクトが無駄になってしまいます。
そうならないためにも、プロジェクトの比較的早い段階、具体的にはキックオフに続く第2回、第3回のプロジェクト会議で、このフレームワーク作業をじっくりと行うことをお勧めします。この作業を通じて、メンバー間の意識を統一し、これから目指す「人を育てる人事制度」の全体像を共有することが、プロジェクト成功のための強固な基盤となります。
3.全員で意見を出し合う:フレームワークシート(アンケート)の活用
フレームワーク作業を進める上で、まず最初に行うのが、関係者からの意見収集です。人事制度は、社長やコンサルタントだけが作るものではありません。経営者、幹部社員、管理者、そして現場の社員まで、関係する多くの人たちが制度を理解し、運用に関わっていく必要があります。だからこそ、制度設計の最初の段階から、できるだけ多くの人の意見を聞くことが大切なのです。
人を育てる人事制度では、プロジェクトメンバーだけでなく、さらに広く、貴社の管理者層を中心に20人程度の社員の皆さんにご協力をお願いし、「フレームワークシート」というアンケートに記入していただきます。これは、会社に対する日頃感じていることや、人事制度に対する考え、期待などを自由に書いてもらうためのものです。
フレームワークシートの具体的な質問項目は、例えば次のようなものです。
①企業の存続と発展は、社員にとってどのような意味を持つとお考えですか?
- これは、単に会社が大きくなることが良い、という経営者側の視点だけでなく、社員一人ひとりのキャリアや生活、幸せと会社の成長がどう結びついているのか、社員自身の言葉で考えてもらうための質問です。会社への帰属意識や、働くことの意義を改めて問い直すきっかけとなります。会社の発展が自分事である、と感じられるかどうかが、その後の主体的な関わり方に大きく影響します。
②「これから」わが社に対してお客様や世の中の動きはどのように変わって行くとお考えでしょうか?
- これは、会社を取り巻く外部環境の変化について、現場で働く社員の皆さんがどのように感じているかを把握するための質問です。お客様との接点が多い営業担当者、技術の変化を感じやすい製造や開発担当者など、それぞれの立場からの気づきや予測は、経営層だけでは得られない貴重な情報となります。これが、今後会社として「どんな能力を持った人材が必要になるか」「どんな行動を評価すべきか」を考える上で、非常に重要な示唆を与えてくれます。
③当社が他社に打ち勝ち、発展してゆくには、各部門でどのような課題が必要でしょうか。また、当社の強みはどのような点にあるとお考えでしょうか?
- これは、会社や各部門が抱える具体的な課題や、逆に他社にはない強みについて、社員の皆さんの認識を聞く質問です。技術的な課題、営業上の課題、管理・運営上の課題など、現場ならではのリアルな声が集まるはずです。この課題こそが、新しい人事制度で「能力開発」や「行動目標」として取り上げるべき重点項目となります。また、当社の「強み」を改めて認識することは、その強みをさらに伸ばすために、人事制度でどのように支援していくべきかを考える出発点になります。
④当社の「今まで」の人事制度(人の採用や配置、社員教育や人事評価、給与や待遇、人間関係、社風等々)を考えた時、最も大きな特徴は何でしょうか?
- これは、過去から現在までの人事の仕組みや慣習について、社員の皆さんがどう感じているかを率直に聞く質問です。良い点、改善してほしい点、漠然とした不満など、様々な意見が出てくるでしょう。これが、新しい制度で解決すべき「問題点」や、「社員が期待している変化」を特定する上で役立ちます。例えば、「評価が曖昧で、自分がなぜこの給料なのか分からない」「頑張っても評価されないと感じる」といった意見が出れば、評価制度の透明性や納得感を高めることが重要なテーマとなります。
⑤「これから」の人事制度は、何を最も大切にすべきでしょうか?
- これは、新しい人事制度に何を期待するのか、社員の皆さんの希望や要望を直接聞く質問です。給与の公平性、能力開発の機会、評価の納得感、働きがいの向上など、様々なキーワードが出てくるはずです。私たちが目指す「人を育てる人事制度」という方向性が、社員の皆さんの期待とどのように重なり合うのかを確認し、制度設計の際の重要な指針とします。
⑥あなたがこのプロジェクトに期待する事など、その他なんでもご意見をお聞かせ下さい。
- 自由に意見を書いてもらうフリーコメント欄です。アンケートの質問項目にはなかったけれど、どうしても伝えたいこと、プロジェクトへの期待、不安など、社員の皆さんの「生の声」を引き出すための大切な項目です。
これらの質問を通じて、社員の皆さんの会社に対する想い、現状認識、そして未来への期待を多角的に引き出します。
ここで一つポイントとなるのが、このアンケートは記名式で実施するということです。中には「無記名の方が本音が出やすいのでは?」という意見もあるかもしれませんが、私はあえて記名式をお勧めしています。なぜなら、人事制度は「隠す」ものではなく、オープンに議論し、みんなで作り上げていくものだと考えているからです。自分の意見に責任を持ち、オープンに発言できる企業文化を育むためにも、最初の意見収集から記名式で行うことが有効だと考えています。もちろん、記入いただいた内容の取り扱いには十分配慮し、安心して本音を書いてもらえるような雰囲気づくりが大切です。
4.集めた意見を「見える化」し、共通理解を深めるカードワーク
さて、社員の皆さんから集めたフレームワークシートの回答は、まさに貴社の「宝の山」です。しかし、集めただけでは意味がありません。ここから、共通の認識や重要なテーマを浮かび上がらせる作業が必要です。そこで行うのが、プロジェクトメンバーによる「カードワーク」です。
カードワークは、集計したアンケート結果を基に行います。まず、回答用紙に書かれている意見やキーワードを、一枚ずつ小さなカードに書き写していきます。この時、抽象的な言葉ではなく、できるだけ具体的な内容で、そして「自社の言葉」で書くことが大切です。他の会社でも通用する一般論ではなく、貴社の現場で実際に使われている言葉、社員の皆さんが感じている「ココロや本音」を大切にカードにするのです。例えば、「もっと協調性が必要」ではなく、「〇〇部の△△さんと□□の情報を共有できるようになりたい」のように、具体的な行動や状況がイメージできる言葉で書きます。
次に、これらのカードを模造紙の上に広げ、似たような意見や関連するテーマごとにグループ分けしていきます。最初は小さなグループから始め、徐々に大きなグループにまとめていきます。この作業を通じて、個々のバラバラに見えた意見が、いくつかの大きなテーマに集約されていくのが分かります。
グループができたら、それぞれのグループに代表するような「見出しカード」をつけます。例えば、「お客様のニーズの変化」「部門間の連携不足」「評価への不満」「能力開発の機会創出」といった見出しです。さらに、グループ間の関係性を矢印で結んで、意見や課題の構造を図示化していきます。
このカードワークの過程で、プロジェクトメンバーはアンケートに書かれた一つひとつの意見を読み上げ、その「ココロ」を理解しようと努めます。なぜ、社員はそう感じているのか?その意見の背景には何があるのか?といったことを話し合います。この議論を通じて、メンバーは社員の皆さんのリアルな声に触れ、自分たちの会社が抱える課題や、社員が人事制度に何を求めているのかを肌で感じることができます。
そして、カードワークの結果を全体で共有し、最終的な結論や、これから目指すべき人事制度の方向性を大きなカードに書き出します。この時、特に重要となるのが、「企業全体の課題からみた人事制度の役割と方向性」をメンバー全員で確認することです。
具体的には、カードワークの結果を踏まえながら、以下の3つの点について、コンサルタントである私が改めて説明を行います。
①企業の発展は社員自身の幸せのためである。
- 会社が成長し、利益を出すことは、単に経営者や株主のためだけではありません。そこで働く社員の皆さんの雇用の安定、給与や待遇の向上、働きがいの創出、能力開発の機会提供など、社員一人ひとりの幸せに直結しているのです。この最も根本的な目的を、プロジェクトメンバー全員がしっかりと共有します。
②企業発展には人材の育成が欠かせない。
- 企業を取り巻く環境は常に変化しています。競争に打ち勝ち、持続的に発展していくためには、新しい技術や知識を習得し、変化に対応できる能力を持った「人財」が不可欠です。どれだけ優れた経営戦略があっても、それを実行できる社員がいなければ絵に描いた餅になってしまいます。人事制度の最も重要な役割は、この「人材育成」を会社の仕組みとして定着させることなのです。
③人事制度の役割は人材の育成である。
- 従来の人事制度は、社員を「評価」し、「振り分け」、それに基づいて「給与を決める」といった側面に重点が置かれがちでした。しかし、特に中小企業においては、限られた人数の中で「誰が出来る、出来ない」と振り分けてもあまり意味がありません。それよりも大切なのは、今いる社員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、育てていくことです。新しい人事制度は、まさにこの「人を育てるためのしくみ」なのです。評価も給与も、すべては社員の成長を促し、会社の利益に貢献してもらうための手段として位置づけられます。
これらの点を改めて確認し、プロジェクトメンバー全員で「人を育てる人事制度」を目指すという共通理解を醸成します。単なる「評価制度」「給与制度」を作るのではなく、「社員が育ち、会社が発展する」ための仕組みを作るのだ、という強い意志と目的意識を共有することが、このフレームワーク作業の最大の成果と言えるでしょう。
5.フレームワーク作業が、その後の制度設計を大きく左右する
フレームワーク作業で目的や方向性が明確になり、メンバー間の共通理解が深まれば、その後の制度設計、例えば「資格等級制度」や「行動評価制度」「給与制度」の構築が非常にスムーズに進みます。
「ウチの会社では、将来どのような能力を持った人材が必要なのか?」「会社として社員に期待する行動や努力は何なのか?」「それを評価するためには、どんな項目を、どう見れば良いのか?」「社員の成長をどう給与に反映させるのか?」といった具体的な議論をする際に、フレームワーク作業で共有した目的や価値観が「軸」となります。この軸があるからこそ、多様な意見が出ても、立ち返るべき原点があり、ブレずに議論を進めることができるのです。
逆に、このフレームワーク作業を疎かにしてしまうと、後々になって「あれ?そもそも何のためにこの制度作るんだっけ?」「この評価項目って、ウチの会社が本当に大切にしていることと合ってるのかな?」といった疑問や迷いが生じやすくなります。
また、この作業を通じて社員の皆さんの意見を聞き、それを制度設計に反映させていくプロセスそのものが、社員の皆さんの働きがいを高めることにも繋がります。自分の意見が会社の制度作りに活かされている、自分たちの会社は「人」を大切に考えている、と感じることは、社員のエンゲージメントを高める上で非常に重要です。
私たちが目指す「人を育てる人事制度」は、決して社員を「脅す」ものではありません。成果が出せないから減給、リストラ、といった「脅しの人事」ではなく、社員を「資産」と考え、その能力を最大限に引き出し、成長を支援するための仕組みです。今回のフレームワーク作業は、この「育てる」という基本理念を、プロジェクトメンバーだけでなく、意見を聴取した社員の皆さんとも共有する大切な機会なのです。
6.まとめ
今回は、「人を育てる人事制度」策定プロジェクトにおけるフレームワーク作業の重要性について、詳しくご説明しました。この作業は、プロジェクトの目的と方向性を明確にし、関係者間の共通理解を深めるための非常に重要なステップです。社員の皆さんの生の声を聞き、それを基に会社の課題や目指すべき姿を「見える化」することで、貴社独自の人事制度を構築するための強固な基盤が築かれます。
特に、中小企業においては、トップダウンで一方的に制度を押し付けるのではなく、社員も巻き込み、共に考え、作り上げていくプロセスが、その後の制度のスムーズな運用や、社員の自律的な成長、そして会社全体の活力向上に繋がります。
このフレームワーク作業で培った共通理解と協力体制は、その後の資格等級制度、行動評価制度、給与制度といった具体的な制度設計の段階で、必ずや貴社の大きな力となるはずです。
次回からは、いよいよ社員の能力を段階で示す「資格等級制度」づくりに入っていきます。今回明確になった「ウチの会社で必要とされる能力、期待される行動」といった視点が、次のステップでどのように活かされるのか、ぜひ楽しみにしていてください。
貴社が「人を育て、社員が輝き、会社が発展する」ための人事制度を共に作り上げていけることを、心から願っております。
次回もどうぞよろしくお願いいたします!
投稿者プロフィール

-
木戸社会保険労務士事務所の三代目の石田厳志と申します。当事務所は、私の祖父の初代所長木戸琢磨が昭和44年に開業し、長年に渡って企業の発展と、そしてそこで働く従業員の方々の福祉の向上を目指し、多くの皆様に支えられて社会保険労務士業を行ってまいりました。
当事務所は『労働保険・社会保険の手続』『給与計算』『就業規則の作成・労働トラブルの相談』『役所の調査への対応』『障害年金の請求』等を主たる業務としており、経営者の困り事を解決するために、日々尽力しています。経営者の方々の身近で頼れる相談相手をモットーに、きめ細かくお客様目線で真摯に対応させていただきます。
最新の投稿