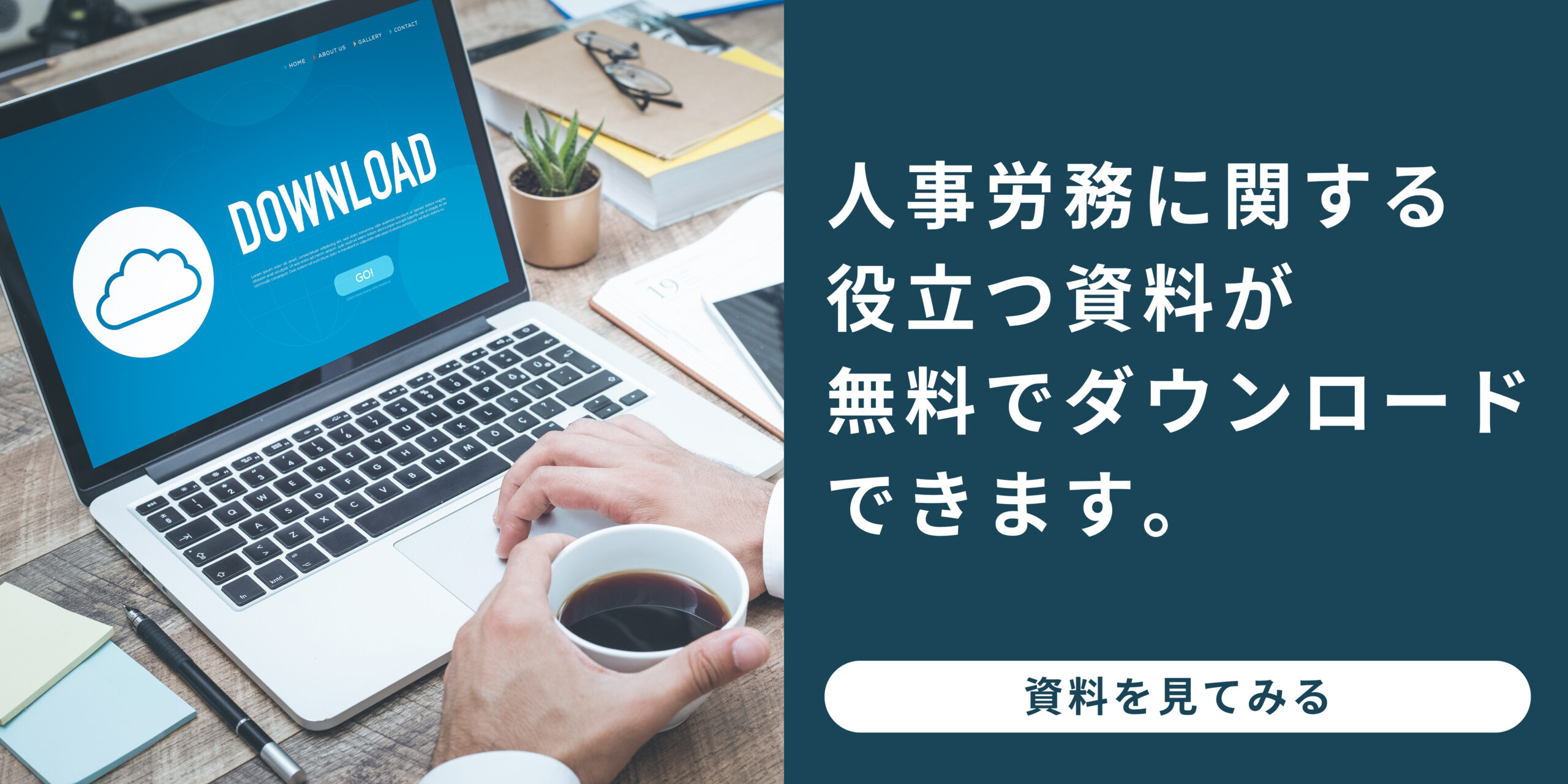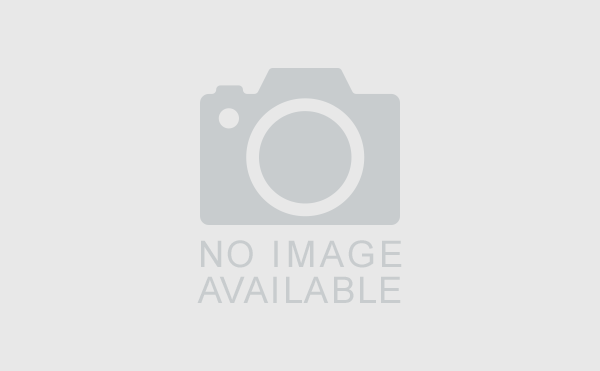第2回「人を育てる人事制度」プロジェクト方式による導入
1.はじめに
前回は、これからの時代、中小企業にとって「人を育てる人事制度」がいかに必要不可欠かについてお話ししました。人材確保が難しくなり、採用した若い人に長く働いてもらうのが一層困難になる中で、既存社員の定着と育成、そして組織全体の活性化が、企業の持続的な成長の鍵を握るからです。
さて、頭では必要性を理解したとしても、「じゃあ、どうやってその人事制度を作るんだ?」という疑問が当然湧いてくるでしょう。大企業のように専任の人事部があるわけでもない、社長自身も現場の仕事を兼務している…そんな状況が多い私たち中小企業にとって、人事制度の構築は一見ハードルが高く感じられるかもしれません。
でも、ご安心ください。今回の第2回では、その具体的な第一歩として、「プロジェクト方式」で人事制度を作る、という方法についてお話ししたいと思います。なぜこの方法が良いのか、誰を巻き込むべきか、そして最初の会議である「キックオフ」で何をするのかを詳しく説明いたします。
2.なぜ人事制度づくりをプロジェクト方式で行うのか?
まず、「人事制度づくり=社長か総務担当者一人が頑張る」という考え方は、残念ながらあまりうまくいきません。なぜなら、人事制度は単なる「規則集」ではなく、「人という資産を活用するためのマネジメント」のしくみ であり、社員一人ひとりの能力向上やキャリア形成に対する企業の真剣な取り組みを示すものだからです。そして、何より重要なのは、その制度を社員が理解し、運用できること。一人の人間が作った制度は、往々にして現場との間に乖離が生じやすいのです。
人事制度の策定作業は、プロジェクト方式、つまり社長や幹部社員、管理者、そして一般社員まで、なるべく多くの人に関わってもらいながら作成・整備していく必要があります。
①制度への理解と浸透のため: 制度を作るプロセスに多様な立場の社員が関わることで、制度の意図や内容が社内に浸透しやすくなります。自分たちの手で作ったという意識が芽生え、受け入れられやすくなるのです。
②運用体制の構築: 制度は作って終わりではありません。日々の運用が非常に重要です。プロジェクトを通して、制度を運用する側の管理者や社員が制度を深く理解することで、適切な運用が可能になります。特に、管理者の部下育成・管理能力向上は、このプロジェクトの大きな成果の一つです。
③多様な視点の取り込み: 経営層だけでは見えにくい現場の実態や社員の意見を取り入れることができます。これにより、より実態に即し、社員にとって納得性の高い制度を構築できます。
④企業文化の醸成: 人事制度は「企業風土」や「企業文化」といった組織の価値観や行動規範を作り出すもの。やる気のある社員、協力する社員、学習し向上する社員が当たり前となるような企業文化を育てる 制度は、皆で作り上げることでその力が強化されます。
⑤当事者意識の醸成: 人事制度は、決して経営コンサルタントや総務部長が決めたことを行うための制度ではありません。社員や管理者が自分たちで能力と行動の目標を設定し、皆で実践してゆこうとする活動。つまり、「自律社員」を作り出すことが真の目的 であり、そのスタートとして、自分たち自身が制度作りに参加することが重要なのです。「われわれ自身が業界のプロであり、自社の事情をもっともよく知っている人間です。」 この心構えが大切です。
このように、人事制度づくりを「プロジェクト」として進めることは、単に制度を作るだけでなく、社員を巻き込み、育て、組織を活性化するプロセスそのものなのです。
プロジェクトの規模としては、6~10人程度、または8~12人程度 が適切であり、あまり大人数としない方が作業が進みやすいです。
3.プロジェクトチームのメンバー構成と役割
では、どのようなメンバーでプロジェクトチームを構成すれば良いのでしょうか。私は、以下のメンバー構成を推奨します。
- 経営者層: 少なくとも一人は参加してもらうべきです。理想的には社長自身がメンバーの一員となります。ただし、社長はリーダーとはせず、議論の交通整理役に徹することが重要です。これにより、他のメンバーの発言を促し、メンバーの意見を尊重する姿勢を示すことができます。経営者の参加は、プロジェクトへの会社のコミットメントを示すと同時に、制度が経営戦略と連動するための不可欠な要素です。総務部門の参加も望ましいとされています。
- 部門長・No.2 (部門のNo.2): 彼らが中心メンバーとなります。現場の実情を最もよく知っており、制度が現実的に運用できるかを判断する上で非常に重要な役割を果たします。各部門から1、2名を選定します。
- 一般社員(若手、女子社員など): 社員全体の代表となるよう、若手や女性社員もメンバーに加えることが推奨されています。これにより、多様な視点を取り入れ、幅広い社員の納得感を得やすくなります。
- 労働組合: もし社内に労働組合がある場合は、必ず幹部をメンバーに加える必要があります。
メンバー選定には留意点もあります。社長の息子さんをリーダーにしない、親戚や奥さんはメンバーにしてもリーダーにはしない、最近入社した若手のエリート社員もリーダーにしない、古参の頑固な部長などは適当に流す(無理強いしない)といった留意点です。これは、プロジェクトがスムーズに進み、かつ実効性のある制度にするための現実的な配慮と言えるでしょう。
このプロジェクトチームは、社員の能力によって資格等級を決定する制度(資格等級制度)、社員全員の業務遂行を評価する制度(行動評価制度)、社員の能力及びキャリアを向上するための制度(能力開発制度)、そして資格と評価によって給与を決定する制度(給与制度)を、皆で理解し、運用できるように作り上げていきます。
4.経営者の意思決定と導入の意義の確認
プロジェクトを始める前に、最も重要なステップがあります。それは、経営者自身が人事制度導入の必要性を深く理解し、明確な意思決定をすることです。まず、経営者の人事制度に対する認識を高め、時代に即した制度の必要性を理解することが重要です。
なぜなら、企業発展の原動力は「ビジネスモデルや戦略の良否」と「社員の能力」がうまくかみ合うことにかかっており、これからの競争力は社員の能力が大きく影響するからです。また、社員の働きがいの面からも、能力向上やキャリア形成に対する真剣な取り組みが必要不可欠 となる時代です。
そして、適切な人事制度の策定は、新規採用者の早期退社、優秀な社員の他社への流出、求人の困難さ、組織風土の悪さなど、企業が抱えるさまざまな課題解決に必要な人事戦略 でもあります。社員の最大の関心事の一つである給与についても、適切な評価に基づく決定は避けられない経営課題 です。
このように、人事制度は単なる管理ツールではなく、「人を育てること」を「しくみ」として制度化 し、企業の成長と発展を支える根幹となるものであることを、経営者自身が深く認識する必要があります。この経営者の強い意思と理解が、プロジェクト成功の成否を分けると言っても過言ではありません。この段階で、人事制度の導入によって何を目指すのか(例:公正な評価、望ましい社員像の提示、能力向上機会の提供、管理者の育成、働きがいの向上、経営改善、企業風土の醸成など)を改めて確認することが重要です。
5.キックオフとその進め方
経営者の意思決定がなされ、プロジェクトメンバーが決定したら、いよいよプロジェクトの最初の会議、「キックオフ」を開催します。この会議で、プロジェクトの船出を皆で祝い、今後の活動への期待を高めます。
キックオフ(約1.5時間)での主な作業内容は以下の通りです。
①メンバーの確認: 参加メンバーと、リーダー、サブリーダー、事務局を確認します。
②心構えについて: プロジェクト活動を進める上での「心構え」を共有します。「自由な討論」「メンバーは平等」「社員みんなのために考える」「人の意見に耳を傾け、新しいアイデアを生み出す」「他者のアイデアを取り上げて発展させる(人の褌で相撲を取るを推奨)」「リーダーは指導者ではなく交通整理役」「自分たちが自社の専門家である」といった点を共有しましょう。気楽に、しかし真剣に、皆で意見を出し合える雰囲気作りが重要です。
③スケジュールの確認: 今後のプロジェクトの日程や時間、場所を確認し、共有します。
④作ろうとしている「人事制度」の概要を理解する: 配布資料などを使い、今回作ろうとしている「新しい人事制度」の考え方や進め方について説明します。特に、この人事制度が以下の4つの主要な制度から構成されていることを理解してもらいます。
- 資格等級制度: 社員の能力向上を段階的に資格等級で表現するもの。仕事の難易度や責任などに応じて社内資格を策定し、社員は能力レベルに応じて格付けされます。
- 行動評価制度: 各人の努力や業績を評価する方法を定めたもの。社員の職務遂行能力やその発揮度、勤務態度などを公正に把握し、昇給・昇格などの処遇に反映させるとともに、能力開発や適正配置に活用することを目的とします。
- 能力開発制度: 各人の能力を高める仕組みについて定めたもの。会社が必要とする能力開発や人格形成を体系的、計画的、継続的に行うためのものです。個人目標設定、通信教育、社内・外部研修、OJTなどが含まれます。
- 給与制度: 能力と努力に基づく給与の決め方について定めたもの。資格等級と評価結果に基づいて、人件費予算の範囲内で昇給額や賞与額を公正に決定できるしくみを目指します。
⑤次回作業の準備(フレームワークのためのアンケート依頼): 第2回で実施する「フレームワークづくり」の準備として、プロジェクトメンバーを含めた約20名程度の管理者や役員に、アンケートへの記入と回収をお願いします。このアンケートは、企業の課題、強み、過去の人事制度の評価、今後の人事制度に最も大切にすべきこと、プロジェクトへの期待などを問うものです。このアンケートを「記名式」とすることを推奨します。その理由として「名前を隠してしか意見が言えない会社にはしたくない」という意図を伝えるためです。このアンケートこそが、今後の制度づくりの基本方針を決める重要な資料となります。
キックオフでは、これらの内容を共有し、プロジェクトメンバー全員で「自社に役立つ人事制度」 を作り上げるという共通認識を持つことが目的です。シンプルで、運用しやすい制度を目指すことが大切です。
6.まとめ
いかがでしたでしょうか。人事制度づくりは一人の天才が作り上げるものではなく、社長以下、皆で知恵を出し合い、協力して作り上げていく「プロジェクト」なのだということがお分かりいただけたかと思います。最初のキックオフで、その目的とプロセス、そして皆で取り組む意義を共有することが、今後の活動を円滑に進める上で非常に重要です。
次回は、このキックオフで宿題として依頼したアンケート結果を基に、いよいよ「フレームワークづくり」に取り組みます。我が社はどんな会社で、どんな課題があり、どんな人材を求めているのか…。制度の土台となる重要な話し合いを進めていきます。
投稿者プロフィール

-
木戸社会保険労務士事務所の三代目の石田厳志と申します。当事務所は、私の祖父の初代所長木戸琢磨が昭和44年に開業し、長年に渡って企業の発展と、そしてそこで働く従業員の方々の福祉の向上を目指し、多くの皆様に支えられて社会保険労務士業を行ってまいりました。
当事務所は『労働保険・社会保険の手続』『給与計算』『就業規則の作成・労働トラブルの相談』『役所の調査への対応』『障害年金の請求』等を主たる業務としており、経営者の困り事を解決するために、日々尽力しています。経営者の方々の身近で頼れる相談相手をモットーに、きめ細かくお客様目線で真摯に対応させていただきます。
最新の投稿
 三代目のブログ2026年1月1日第8回:行動評価制度の設計 (2) – 評価要素と手続き
三代目のブログ2026年1月1日第8回:行動評価制度の設計 (2) – 評価要素と手続き 三代目のブログ2025年12月1日第7回:行動評価制度の設計 (1) – 目的と基本構造
三代目のブログ2025年12月1日第7回:行動評価制度の設計 (1) – 目的と基本構造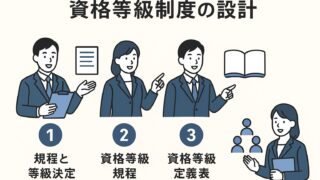 三代目のブログ2025年11月1日第6回:「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (3) ― 規程と等級決定
三代目のブログ2025年11月1日第6回:「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (3) ― 規程と等級決定 三代目のブログ2025年10月1日第5回「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (2) – 仕事しらべ
三代目のブログ2025年10月1日第5回「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (2) – 仕事しらべ