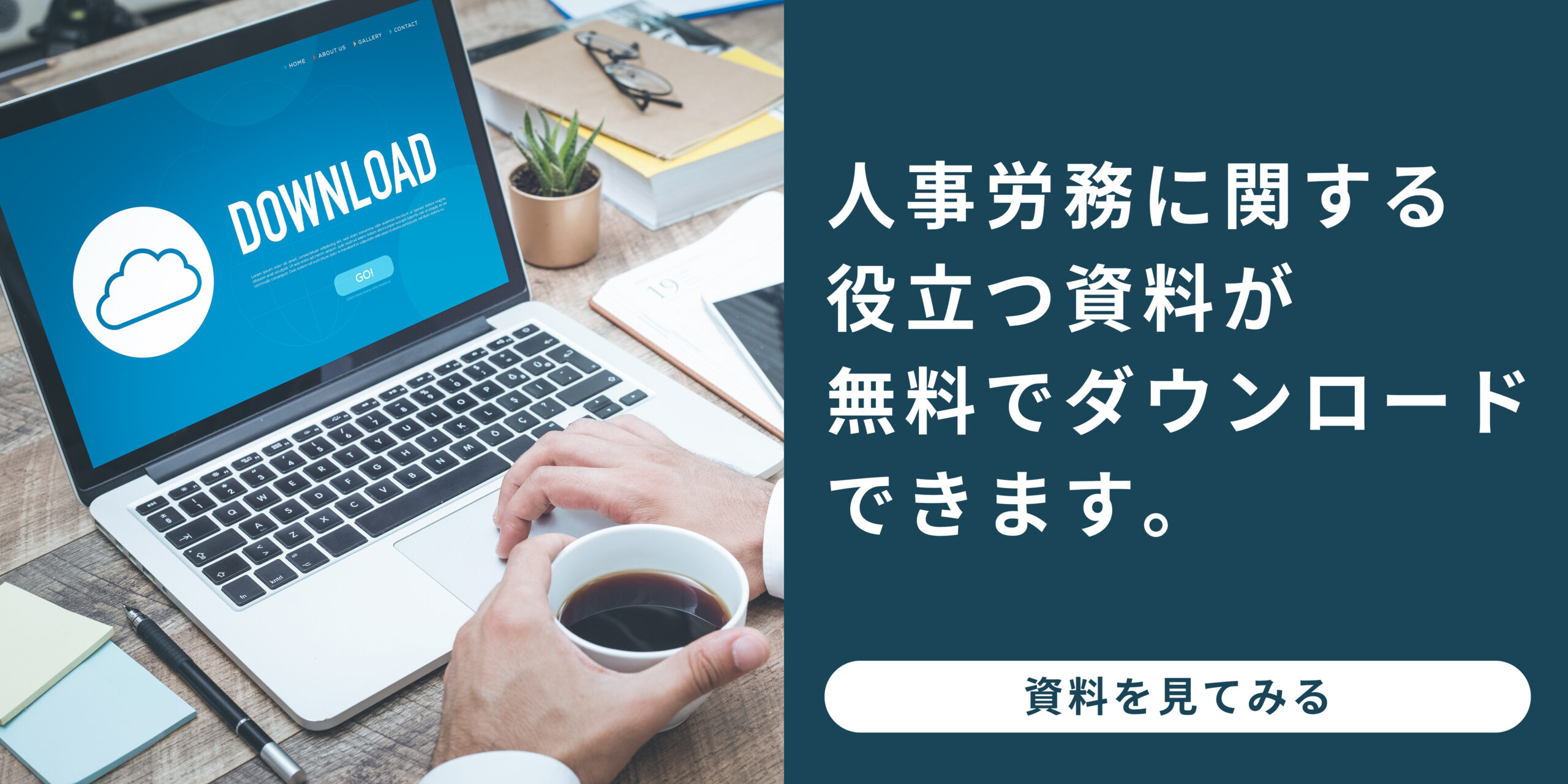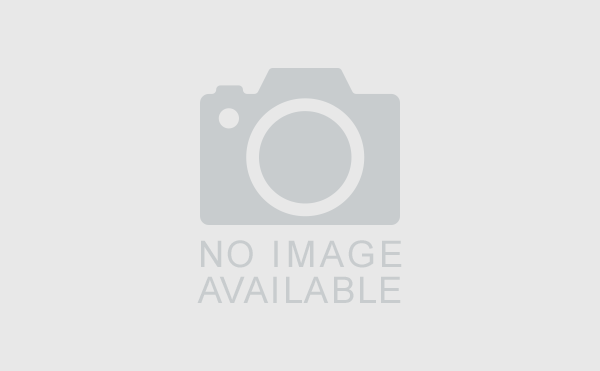第4回「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (1) – 等級数の決定と組織
1.はじめに
前回は、新しい人事制度をプロジェクト方式で進めることの重要性や、その最初のステップである「キックオフ」についてお話ししました。社員の皆さんを巻き込み、共に制度を作り上げていくことの大切さを感じていただけたかと思います。
さて、今回はいよいよ人事制度の具体的な中身に入っていきましょう。新しい人事制度は主に「資格等級制度」「行動評価制度」「能力開発制度」「給与制度」の4つの柱で構成されます。今回は、その最初の柱である「資格等級制度」の設計について、特に「等級数の決定」と「組織」に焦点を当ててお話ししたいと思います。
資格等級制度は、社員の皆さんにとって、ご自身の成長ステップや会社でのキャリアパスを明確に示す、非常に大切な制度です。そして、社長である皆様にとっては、社員の能力を体系的に把握し、将来の人材育成計画を立てる上での基盤となります。
2.社員の成長ステップを示す「資格等級制度」の目的
まず、資格等級制度は何のために作るのでしょうか。一言で言えば、これは「社員の能力によって資格等級を決定する制度」です。そして、その一番の目的は、単に社員をランク付けすることではなく、社員の能力向上を段階的に資格等級で表現し、社員自身の「成長ステップ」を明確に示すことにあります。
考えてみてください。社員の皆さんは、入社してから少しずつ仕事を覚え、経験を積み、能力を高めていきます。その過程で、「自分は今どのくらいのレベルなのか」「次に目指すのはどのレベルなのか」といったことが分からなければ、モチベーションを維持するのは難しいでしょう。
資格等級制度は、まさにその羅針盤となるものです。例えば、新しい制度では、資格等級を1級から6級、あるいは8級まで設定します。1級は「定型業務はできるが、トラブル処理などに必要な経験と知識がまだ不足している初級一般社員」、2級は「経験と知識が十分あり、すべての仕事が一人ででき、かつある程度のトラブル処理ができる中級一般社員」、3級は「業務に精通し、かつ部下の指導、育成ができる指導職」といったように、それぞれの等級に求められる能力レベルを定義していきます。
このように、等級という形で能力レベルを明示することで、社員は自分が今どの段階にいるのか、そして次の等級に上がるためにはどのような能力や経験が必要なのかを具体的に理解できます。これは、社員一人ひとりが自身のキャリアパスを描き、能力開発の目標を設定する上で非常に役立ちます。つまり、資格等級制度は、社員の「やりがい」や「働きがい」にも繋がる重要な「しくみ」なのです。
以前の評価制度が「脅し」になっていたという話がありましたが、新しい人事制度はそうではありません。社員を単なるコストや機械のように扱うのではなく、「人として扱い、人の持つ能力を引き出し、発揮してもらう」ことを目指しています。資格等級制度は、この「人を育てる人事」の考え方を具現化する最初のステップなのです。
3.適切な等級数の決定:なぜ6等級または8等級なのか
さて、資格等級制度を導入するにあたって、最初に決めなければならない重要なことの一つが、等級の数です。社長の皆様は、「うちの会社は社員が少ないから、そんなにたくさんの等級はいらないんじゃないか?」と思われるかもしれません。しかし、私としては「できるだけ6または8等級に設定」することを推奨します。たとえ今の社員数が少なく、役職の段階がそれほど多くなくても(例えば部長、課長、係長のように3段階しかない場合でも)、等級数は6段階に設定することを推奨します。
これは、資格等級制度が単に現在の役職を示すものではなく、社員の「成長ステップ」を示すものだからです。等級数をある程度細かく設定することで、社員はより具体的な次の目標を見つけやすくなります。例えば、3等級しかない場合、社員が次の等級に上がるまでの道のりが遠く感じられるかもしれません。しかし、6等級や8等級であれば、1つ上の等級がより身近な目標となり、継続的な努力を促すことができます。
等級は、社員の能力によって決まるものであり、役職は組織の必要性によって決まるものです。ですから、「役職=資格等級」と固定的に考える必要はありません。極端な話、まだ役職についていない一般社員であっても、能力が高ければ高い等級に格付けされることもあり得ます。もちろん、一般的には等級が上がると役職に就く能力があるとみなされ、昇進の機会が増えることには繋がります。
中小企業の場合、今の組織図がシンプルで役職数が少ないことはよくあります。それでも、社員の成長を後押しするため、そして将来の会社の発展を見据えて、6等級または8等級というある程度細やかな成長ステップを用意することが効果的です。
等級数を決定する際には、社長や専務、常務といった経営層は等級の対象から除くのが一般的です。ただし、取締役として特定の部門の部長を兼務しているような方は、等級の対象に含めることがあります。また、後ほど詳しく触れますが、管理職コースと専門職コースを設けるかどうかも、等級数を考える上でのポイントになります。
等級数を決定する作業は、プロジェクトメンバーと共に、会社の現状の組織や将来の組織図を考慮しながら行います。これも社員を巻き込むプロセスの一環ですね。
4.将来の組織図の検討と等級との関連
人事制度、特に資格等級制度を考える上で、会社の「将来の組織図」を検討することは非常に重要です。なぜなら、資格等級制度は社員の成長ステップを示すものですが、その成長は会社の将来の方向性や組織の必要性と結びついているからです。
私たちはフレームワークづくりの活動で、会社の現状の課題や将来の方向性について話し合いましたね。その中で、将来の事業内容や、事業を進めていくための組織について考えた方もいらっしゃると思います。資格等級制度は、その将来の組織で必要となるであろう人材を育成するための基盤となるのです。
例えば、将来的に工場や店舗を増やす計画がある、あるいは新しい事業分野に進出することを考えている、といった場合です。当然、それに伴って組織の体制も変わるでしょう。新しい部門ができたり、責任者のポストが増えたりします。
資格等級制度を設計する際には、こうした「近未来のあるべき組織」を想定し、そこで必要とされる役割や能力レベルを考慮に入れることが大切です。現在の組織図だけでなく、3年後、5年後を見据えた「将来の想定組織図」を作成することも有効です。
将来の組織図と等級を結びつけて考えることで、私たちは以下の点を明確にすることができます。
- 将来必要となるポストに就くには、どの等級レベルが必要か? 例えば、将来の新しい事業部の責任者には、現在のどの等級以上の能力が求められるか、といったことを想定します。
- 将来必要となる新しい仕事や役割には、どの等級レベルの社員が対応できるようになるべきか? フレームワークや仕事しらべの活動で、将来必要となる課題や仕事について話し合います。これらの仕事は、どの等級の社員が行うのが適切かを考えることで、等級の定義や社員の能力開発目標がより明確になります。
- 社員が将来の組織で活躍するためには、どのような能力開発が必要か? 将来の組織を見据えて設定された等級と、それに求められる能力が明確になることで、社員一人ひとりの能力開発計画や、会社全体の研修計画を具体的に立てやすくなります。
もちろん、先ほど申し上げたように、資格等級と役職は固定的なものではありません。しかし、将来の組織を見据えて等級を設計することは、長期的な人材育成戦略の視点から非常に理にかなっています。社長として、会社の将来像を社員と共有し、共にその実現を目指す上で、資格等級制度は強力なツールとなります。
5.管理職コースと専門職コースの設定
中小企業では、社員のキャリアパスが限られていると感じてしまうことがあります。「出世=管理職」という道しかない場合、管理職になりたい人にとっては良いかもしれませんが、専門性を追求したい人にとっては魅力的に映らないかもしれません。
新しい資格等級制度では、こうした課題に対応するために、「管理職コース」と「専門職コース」を設定することを検討します。
管理職コースは、文字通り部下を管理し、組織を率いる役割を担うためのキャリアパスです。部長や課長、係長といった役職と関連付けられることが多いでしょう。管理職には、単に自分の業務をこなすだけでなく、部下の育成や管理、部門目標の設定・達成、組織の統制といった能力が求められます。資格等級制度における上位の等級(例えばⅢ級以上)は、管理職としての能力や役割が考慮された定義になることが一般的です。
一方、専門職コースは、特定の分野で高い専門性を持つ社員のためのキャリアパスです。例えば、製造業における高度な技術者、デザイン会社における優れたデザイナー、IT企業におけるシステムエンジニアなど、その分野における深い知識や経験、特殊な技能を持つ人材です。これらの社員は、必ずしも管理職に就くことを望まなかったり、あるいは管理職として処遇することが組織的に難しかったりする場合でも、その専門性の高さに応じて高い等級で処遇することを可能にするのが専門職コースの目的です。
専門職コースを設けることで、以下のようなメリットがあります。
- 多様なキャリアパスの提示: 社員は管理職だけでなく、専門家として会社に貢献し、評価される道があることを知ることができます。これにより、様々な志向を持つ社員のモチベーションを高めることができます。
- 専門人材の定着: 高い専門性を持つ社員が、管理職ではないという理由だけで昇進や昇給の機会が限定されると感じてしまうと、他社へ流出するリスクが高まります。専門職コースを用意することで、そうした人材の会社への貢献を正当に評価し、引き留めることができます。
- 組織全体の能力向上: 特定分野の専門家がいることは、会社の技術力や競争力に直結します。専門職コースを設けることで、そうした専門性をさらに高めてもらい、会社全体の能力底上げに繋げることができます。
専門職の等級は、一般職や管理職コースの等級と並行して設定されます。例えば、課長クラスの管理職と同じくらいの能力レベルを持つ専門職には、同じ5級を付与するといった考え方です。
中小企業においては、特定の専門スキルを持つ社員が1人だけ、というケースも少なくありません。そうした場合でも、その専門性を正当に評価し、等級として位置づけることが大切です。
管理職コースと専門職コースを設定するかどうか、どのように等級を割り振るかは、会社の事業内容や将来の方針によって異なります。プロジェクトメンバーと十分に議論し、会社の事情に合わせた設計を行うことが重要です。
6.まとめと次回予告
今回は、新しい人事制度の最初の柱である資格等級制度について、特に「等級数の決定」と「組織との関連性」、そして「管理職コースと専門職コース」についてお話ししました。
資格等級制度は、単なる社員のランク付けではなく、社員一人ひとりの成長ステップを明確にし、能力向上を促すための重要な「しくみ」です。そして、6等級または8等級といったある程度細やかな等級数を設定することで、社員はより具体的な目標を持って働くことができるようになります。さらに、会社の将来の組織図を検討し、そこに必要とされる人材像や役割を等級設定に反映させることで、長期的な視点に立った人材育成が可能となります。最後に、管理職コースと専門職コースを用意することは、多様なキャリアパスを示し、様々な能力を持つ社員のモチベーション向上と定着に繋がるでしょう。
これらの設計作業は、プロジェクト方式で社員の皆さんと共に行います。皆で会社の将来像や必要な能力について話し合い、合意形成を図るプロセスそのものが、社員の制度への理解と参画意識を高めます。社長である皆様は、このプロジェクトの意義をメンバーにしっかりと伝え、議論を促進する役割を担います。
資格等級制度の設計は、人事制度の基盤となる重要なステップです。しかし、これだけでは終わりません。等級を定義したら、次は個々の社員の能力をその等級に当てはめていく作業、つまり「社員の資格等級決定」が必要です。
次回は、今回の等級数や組織の検討を踏まえて行う、「仕事しらべ」という重要な作業について詳しくお話しします。これは、社員の皆さんが実際に行っている仕事を洗い出し、それを整理・分類する作業で、等級定義や評価項目を作成する上で不可欠なステップとなります。
社長の皆様、社員の皆さんを「育てる」人事制度づくりは、一歩ずつ着実に進んでいきます。今回の内容を参考に、ぜひプロジェクトメンバーとの議論を深めていただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに。
投稿者プロフィール

-
木戸社会保険労務士事務所の三代目の石田厳志と申します。当事務所は、私の祖父の初代所長木戸琢磨が昭和44年に開業し、長年に渡って企業の発展と、そしてそこで働く従業員の方々の福祉の向上を目指し、多くの皆様に支えられて社会保険労務士業を行ってまいりました。
当事務所は『労働保険・社会保険の手続』『給与計算』『就業規則の作成・労働トラブルの相談』『役所の調査への対応』『障害年金の請求』等を主たる業務としており、経営者の困り事を解決するために、日々尽力しています。経営者の方々の身近で頼れる相談相手をモットーに、きめ細かくお客様目線で真摯に対応させていただきます。
最新の投稿
 三代目のブログ2026年1月1日第8回:行動評価制度の設計 (2) – 評価要素と手続き
三代目のブログ2026年1月1日第8回:行動評価制度の設計 (2) – 評価要素と手続き 三代目のブログ2025年12月1日第7回:行動評価制度の設計 (1) – 目的と基本構造
三代目のブログ2025年12月1日第7回:行動評価制度の設計 (1) – 目的と基本構造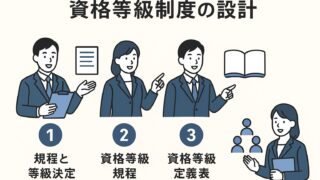 三代目のブログ2025年11月1日第6回:「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (3) ― 規程と等級決定
三代目のブログ2025年11月1日第6回:「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (3) ― 規程と等級決定 三代目のブログ2025年10月1日第5回「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (2) – 仕事しらべ
三代目のブログ2025年10月1日第5回「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (2) – 仕事しらべ