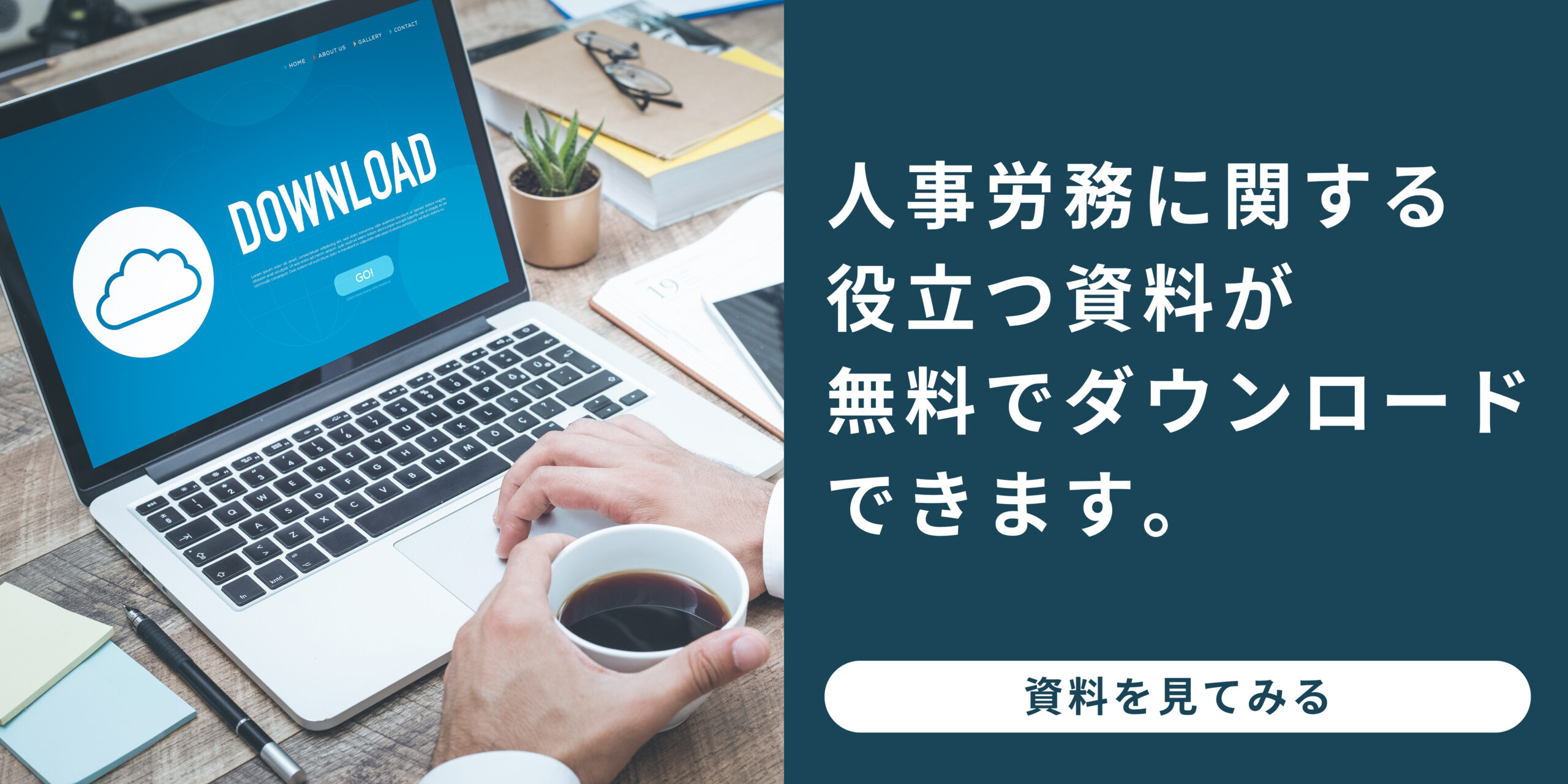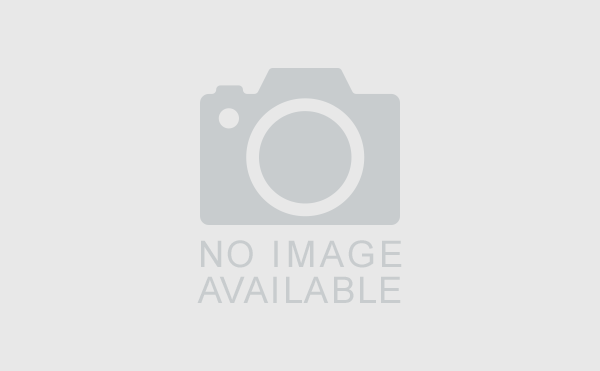知っておきたい!不妊治療と仕事、職場の理解と配慮
1.はじめに
近年、労働力不足が深刻化する中で、従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、長く活躍してもらうための環境整備は、企業の持続的な成長に不可欠です。その重要な要素の一つとして、従業員の多様な働き方を支援することが挙げられます。今、社会全体で、働きながら不妊治療を受ける方が増加傾向にあると考えられています。しかしながら、厚生労働省の調査によると、不妊治療と仕事の両立は決して容易ではなく、約11%もの方が両立を断念し、離職という道を選んでいるのが現状です。これは、企業にとっても貴重な人材の損失であり、看過できない問題と言えるでしょう。
今回は、不妊治療と仕事の両立をサポートするために、企業が知っておくべき基礎知識から具体的な対応策までを網羅的に解説いたします。顧問先の皆様が、従業員一人ひとりの状況に寄り添い、安心して働ける環境づくりを進めるための一助となれば幸いです。不妊治療は、決して他人事ではありません。貴社の大切な従業員も、あるいは将来的にそうなる可能性も十分にあります。本稿を通じて、不妊治療と仕事の両立支援に対する理解を深め、より良い職場環境の実現に向けて共に歩んでいきましょう。
2.不妊治療と仕事の両立を取り巻く現状
①不妊を心配する夫婦の割合と不妊治療の現状
不妊は、決して珍しい問題ではありません。資料によると、不妊を心配したことがある夫婦は39.2%に上り、これは夫婦全体の約2.6組に1組の割合となります。さらに、実際に不妊の検査や治療を受けたことがある(または現在受けている)夫婦は22.7%で、夫婦全体の約4.4組に1組の割合となっており、その割合は年々高まっていることが示されています。この数字からも、不妊治療が現代社会において身近な課題であることが伺えます。
②生殖補助医療による出生児数の増加
不妊治療の中でも、体外受精や顕微授精といった生殖補助医療の技術は進歩を続けており、その利用も広がっています。2022年には、77,206人が生殖補助医療により誕生しており、これは全出生児(770,759人)の10.0%に相当します。つまり、約10人に1人の赤ちゃんが生殖補助医療によって生まれている計算になり、その割合は年々増加傾向にあります。この事実は、不妊治療が多くの夫婦にとって、子どもを持つための重要な選択肢となっていることを示唆しています。
③仕事と不妊治療の両立の難しさと離職の実態
このように不妊治療を受ける方が増える一方で、仕事との両立は依然として大きな課題となっています。不妊治療をしたことがある(または予定している)労働者を対象とした調査では、「仕事と両立している(していた)」と回答した人の割合は55.3%であるのに対し、「仕事との両立ができなかった(できない)」とした人の割合は26.1%に上ります。この「両立ができなかった」と回答した人の中には、「両立できず仕事を辞めた」「両立できず不妊治療をやめた」「両立できず雇用形態を変えた」という方が含まれており、4人に1人以上が仕事と不妊治療の両立に困難を感じている現状が明らかになっています。さらに冒頭でも触れたように、厚生労働省の調査では、11%の方が不妊治療と仕事の両立ができずに離職しているというデータも示されています。
④両立を困難にする具体的な要因
では、なぜ不妊治療と仕事の両立は困難なのでしょうか。厚生労働省の調査によると、その理由として最も多く挙げられているのは、「待ち時間など通院にかかる時間が読めない、医師から告げられた通院日に外せない仕事が入るなど、仕事の日程調整が難しいため」であり、49.3%の方がこの点を課題として挙げています。次いで多いのが、「精神面で負担が大きいため」(44.8%)、「体調、体力面で負担が大きいため」(40.3%)、「通院回数が多いため」(32.8%)となっています。
その他にも、「病院と会社と自宅が離れていて、移動が負担であるため」(20.9%)、「職場の理解やサポートが得られないため」(20.9%)、「仕事がストレスとなり不妊治療に影響がでるため」(20.9%)、「長時間労働であるため」(14.9%)といった要因も指摘されています。これらの要因は複合的に絡み合い、不妊治療を受ける労働者にとって大きな負担となり、仕事との両立を困難にしていると考えられます。また、企業や働く人々自身が、不妊や不妊治療についての認識が十分でないことも、支援制度の導入や利用が進まない一因となっている可能性も指摘されています。
3.中小企業が不妊治療と仕事の両立をサポートする重要性
①従業員の多様な働き方を支援する企業の社会的責任
近年、企業には、性別、年齢、国籍、障がいの有無だけでなく、個々のライフステージや価値観に応じた多様な働き方を支援する社会的責任が求められています。不妊治療を受けながら働く従業員への配慮も、この一環として捉えるべきでしょう。従業員が安心して治療に専念できる環境を提供することは、企業イメージの向上にも繋がり、社会からの信頼を得ることにも繋がります。
②両立支援による従業員エンゲージメントの向上
従業員が不妊治療と仕事の両立に悩むことなく、安心して働き続けられる環境を整備することは、従業員の企業に対するエンゲージメントを高める上で非常に重要です。企業が従業員の個人的な事情に理解を示し、サポート体制を整えることは、「会社は自分のことを大切に思ってくれている」という従業員の安心感や信頼感を生み出し、仕事へのモチベーション向上に繋がります。エンゲージメントの高い従業員は、生産性の向上や企業の成長に大きく貢献することが期待できます。
③優秀な人材の確保と離職防止
前述の通り、不妊治療と仕事の両立が困難であるために離職を選択する従業員は少なくありません。特に、専門的な知識やスキルを持つ優秀な人材が、不妊治療のために離職してしまうことは、企業にとって大きな損失です。不妊治療と仕事の両立支援を充実させることは、このような優秀な人材の離職を防ぎ、長期的な視点での人材確保に繋がります。働きやすい環境は、求職者にとっても魅力的な要素となり、新たな人材の獲得にも貢献するでしょう。
④生産性維持と企業イメージの向上
従業員が安心して不妊治療を受けられる環境は、精神的な負担の軽減や体調不良時の配慮によって、結果的に業務への集中力を高め、生産性の維持にも繋がります。また、不妊治療と仕事の両立支援に積極的に取り組む企業姿勢は、社会的に高く評価され、企業イメージの向上に繋がります。これは、採用活動においても有利に働き、企業の持続的な成長を後押しする力となるでしょう。
⑤ハラスメント防止の観点から
不妊治療に関する職場での無理解は、ハラスメントにも繋がりかねません。不妊治療を受けていることに対する嫌がらせや不利益な扱いは、当然ながら許されるものではなく、法律に触れる可能性もあります。また、直接的な嫌がらせでなくとも、親しい者同士のからかいや冗談が、当事者を深く傷つけることもあります。企業は、不妊治療に対する正しい知識を啓発し、従業員一人ひとりが相手の気持ちを理解し、尊重する職場環境づくりに努める必要があります。
4.職場における具体的な配慮のポイント
①上司(管理職)が理解すべきことと相談対応のポイント
職場の上司となる方は、不妊治療を受けている部下から相談や報告を受ける可能性があります。その際、不妊治療について正しく理解した上で、人事労務担当者や産業保健スタッフなどと連携しながら、以下の点に配慮し、適切な対応を心がけることが重要です。
(1)企業メッセージを伝えることの重要性
まず、「労働者の不妊治療と仕事との両立を支援する」という企業の明確なメッセージを部下に伝えることが大切です。これにより、部下は安心して相談しやすくなり、制度利用への心理的なハードルも下がります。
(2)部下の状況把握と必要なサポートの確認
部下の不妊治療と仕事との両立の実態(不妊治療が仕事に及ぼす影響や今後の治療の見通しなど)を、可能な範囲で把握するように努めます。ただし、プライバシーに関わる情報であるため、部下の意向を尊重し、無理に聞き出すようなことは避けなければなりません。
(3)働き方のニーズの把握
部下が不妊治療との両立のために、どのような働き方を希望しているかを具体的に把握します。例えば、不妊治療休暇制度、フレックスタイム制、テレワークなどの活用、一時的な業務分担の変更、出張の可否など、部下のニーズを丁寧にヒアリングすることが重要です。
(4)プライバシーへの配慮と情報管理
不妊治療に関する情報は、極めてプライベートな情報であることを十分に認識し、部下の意思を尊重しないまま、他の同僚などに知らせたり、詮索したりするようなことがないように細心の注意を払う必要があります。知り得た個人情報は適切に管理し、本人の同意なしに第三者に開示することは絶対に避けなければなりません。相談内容をどこまでの部署や誰に伝えるかについても、事前に部下の意向を確認することが重要です。
(5)自社の支援制度の説明
自社にどのような不妊治療と仕事の両立のための休暇制度や支援制度があるかを、具体的に説明します。制度の内容だけでなく、利用する場合の具体的な申請方法や申請のタイミングについても丁寧に説明することが重要です。
(6)人事労務担当者との連携
必要に応じて、人事労務担当部署や担当者、産業医・産業保健スタッフに確認したいことがないか部下に確認し、必要であれば情報伝達をしたり、直接相談できるように仲介したりすることも上司の重要な役割です。
②同僚が理解し、配慮すべきこと
職場の同僚は、不妊治療を受けている本人やその上司から、不妊治療を受けていることを知らされることがあるかもしれません。その際、以下の点に配慮をお願いします。
(1)不妊治療に関する詮索や不用意な言動を避ける
不妊治療の内容や経過、結果などについて、むやみに詮索したり、立ち入った質問をしたりすることは避けるべきです。良かれと思ってかけた言葉でも、当事者を傷つけてしまう可能性があります。
(2)お互い様の気持ちを持つことの重要性
自身も過去に誰かにサポートしてもらった経験や、将来的にサポートしてもらうことが起こり得ることを理解し、お互い様の気持ちを持って接することが大切です。
(3)ポジティブな職場環境づくりへの協力
不妊治療を含む妊娠・出産などに関する否定的な言動は、ハラスメントの原因や背景になり得ます。ルールがあるから気を付けるのではなく、自分自身が働きやすい職場づくりを担う一員であるという意識を持ち、ポジティブな職場環境づくりに協力しましょう。また、不妊治療を行っている労働者の業務をカバーしている同僚の働き方や業務量の状況を把握し、必要であれば協力し合うことも重要です。
5.企業が導入できる主な支援制度
従業員が安心して不妊治療と仕事の両立を図るためには、企業が様々な支援制度を導入することが有効です。自社の状況に合わせて、以下のような制度の導入を検討してみましょう。
- 不妊治療に特化した休暇制度・休職制度:不妊治療のための通院や体調不良時に利用できる、独自の休暇制度や休職制度を設けることは、従業員の大きな安心に繋がります。
- 年次有給休暇の取得しやすい環境整備(半日・時間単位取得):通院のために柔軟に休暇を取得できるよう、年次有給休暇の半日単位や時間単位での取得を可能にすることは、従業員にとって非常に助かります。
- 柔軟な働き方を支援する制度:
- 短時間勤務制度:治療期間中に一時的に勤務時間を短縮できるようにする制度です。
- テレワーク:自宅など、柔軟な場所で働けるようにすることで、通院の負担を軽減できます。
- 時差出勤制度:出退勤時間を調整できるようにすることで、通院の都合に合わせやすくします。
- 在宅勤務等:オフィスに出勤する必要がない働き方は、体調が優れない時などにも働きやすい選択肢となります。
- 不妊治療費用の助成制度:経済的な負担を軽減するために、会社や健康保険組合が不妊治療費用の一部を助成する制度を設けることも有効です。
- 失効年次有給休暇の積立制度:失効してしまう年次有給休暇を積み立てて、不妊治療のために利用できるようにする制度です。
- 通院・休息時間を認める制度:治療に伴う通院や、体調不良時の休息を就業時間中に認める制度です。
- 不妊治療連絡カードの活用:従業員が不妊治療中であることを企業に伝えやすくし、制度利用の申請などをスムーズに行うためのツールとして、厚生労働省が推奨する「不妊治療連絡カード」の活用を促しましょう。
これらの制度を導入するだけでなく、従業員がこれらの制度を利用しやすいように、職場内の理解を深めることや、業務体制を整備することも重要です。上司自らが不妊治療への理解を深めるとともに、社員一人ひとりが理解を深めることができるよう、研修や情報提供などの取り組みを行うことが望ましいでしょう。また、不妊治療を行っている労働者の業務をカバーしている社員の働き方や業務量の状況を把握し、必要であれば業務体制や業務分担などの見直し、調整を行うことも大切です。
6.従業員が利用できる相談窓口と関連情報
従業員が不妊治療と仕事の両立について悩んだ際に相談できる窓口や、役立つ情報を提供することも、企業のサポートの一環として重要です。以下の情報を従業員に周知しておきましょう.
- 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室):不妊治療と仕事の両立に関するトラブルや相談に対応しています。
- 監督署等の総合労働相談コーナー:解雇、雇止め、ハラスメントなど、あらゆる労働問題に関する相談を受け付けています。
- 厚生労働省の関連情報サイト:
- 働き方・休み方改善ポータルサイト:働き方や休み方の見直しに役立つ情報や、不妊治療に係る特別休暇制度の企業事例などが掲載されています。
- テレワーク総合ポータルサイト:テレワークに関する情報が一元化されています。
- 両立支援のひろば:次世代育成支援対策推進法に基づく情報などが掲載されています。
- あかるい職場応援団:職場のハラスメント予防・解決に関する情報が提供されています。
- 厚生労働省ホームページ「不妊治療と仕事との両立のために」:事業主、労働者向けに様々な情報が発信されています。
- 性と健康の相談センター:不妊症や不育症に関する医学的・専門的な相談や、経験者によるピアサポートが行われています。
これらの相談窓口や情報サイトの連絡先やURLなどを社内イントラネットや掲示板などで周知し、従業員が必要な時にアクセスできるようにしておくことが大切です。
まとめ
本稿は、中小企業の経営者の皆様に向けて、不妊治療と仕事との両立をサポートするための基礎知識と具体的な対応策について解説しました。不妊治療は、貴社で働く従業員も直面している可能性のある身近な課題です。従業員が安心して治療と仕事に取り組める環境を整備することは、従業員のウェルビーイングを高めるだけでなく、企業の持続的な成長にも不可欠です。
今回ご紹介した、不妊治療の現状、基礎知識、企業が両立支援に取り組む重要性、具体的な配慮のポイント、導入できる支援制度、そして相談窓口に関する情報は、貴社が従業員一人ひとりの状況に寄り添い、より働きやすい職場環境を実現するための一助となるはずです。これらの情報を参考に、ぜひ自社に合った両立支援のあり方を検討し、実行に移していただければ幸いです。従業員一人ひとりがその能力を最大限に発揮できる、そんな温かい職場づくりを共に目指しましょう。
投稿者プロフィール

-
木戸社会保険労務士事務所の三代目の石田厳志と申します。当事務所は、私の祖父の初代所長木戸琢磨が昭和44年に開業し、長年に渡って企業の発展と、そしてそこで働く従業員の方々の福祉の向上を目指し、多くの皆様に支えられて社会保険労務士業を行ってまいりました。
当事務所は『労働保険・社会保険の手続』『給与計算』『就業規則の作成・労働トラブルの相談』『役所の調査への対応』『障害年金の請求』等を主たる業務としており、経営者の困り事を解決するために、日々尽力しています。経営者の方々の身近で頼れる相談相手をモットーに、きめ細かくお客様目線で真摯に対応させていただきます。
最新の投稿
 三代目のブログ2026年1月1日第8回:行動評価制度の設計 (2) – 評価要素と手続き
三代目のブログ2026年1月1日第8回:行動評価制度の設計 (2) – 評価要素と手続き 三代目のブログ2025年12月1日第7回:行動評価制度の設計 (1) – 目的と基本構造
三代目のブログ2025年12月1日第7回:行動評価制度の設計 (1) – 目的と基本構造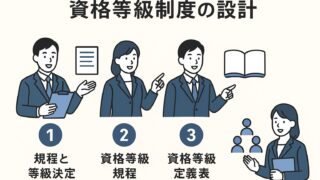 三代目のブログ2025年11月1日第6回:「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (3) ― 規程と等級決定
三代目のブログ2025年11月1日第6回:「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (3) ― 規程と等級決定 三代目のブログ2025年10月1日第5回「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (2) – 仕事しらべ
三代目のブログ2025年10月1日第5回「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (2) – 仕事しらべ