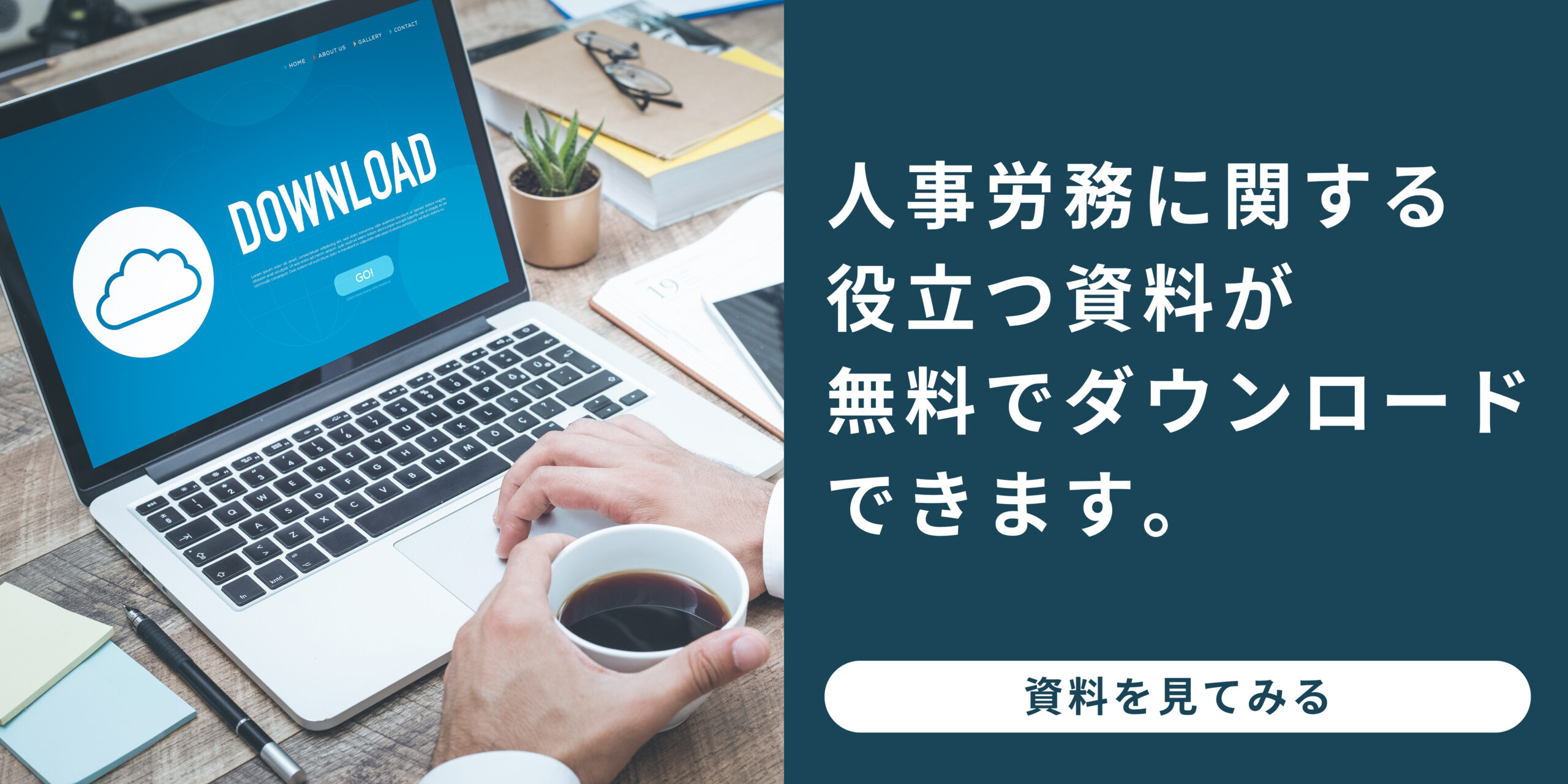令和6年改正育児・介護休業法を完全解説!中小企業が取るべき対応策
1.はじめに
育児や介護と仕事を両立させることは、多くの中小企業の従業員にとって大きな課題です。働き方改革が進む中、令和6年の育児・介護休業法改正は、企業にさらなる対応を求めています。この改正では、柔軟な働き方の推進や休暇取得範囲の拡大といった、現代の多様な働き方に対応する施策が盛り込まれています。本記事では、法改正の詳細を解説し、中小企業が取るべき具体的な対応策についてわかりやすく説明します。
2.改正の概要
(1)改正の主なポイント
令和6年改正では、育児や介護に配慮した働き方を実現するため、以下の内容が盛り込まれています。
①柔軟な働き方の措置の拡充
始業時間の変更やテレワーク制度の導入など、柔軟な働き方を推進するための対応が企業に求められています。
②所定外労働の制限対象拡大
これまでは3歳未満の子どもを対象としていましたが、小学校就学前の子どもまで対象が広がります。
③育児・介護のためのテレワークの努力義務
テレワーク導入を通じて、通勤負担を軽減することが求められています。
(2)段階的な施行スケジュール
今回の改正は段階的に施行されます。
①令和6年5月31日:次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長
②令和7年4月1日:所定外労働の制限対象拡大、テレワーク努力義務化など
③令和7年10月1日:柔軟な働き方措置義務化、個別の意向聴取・配慮の義務付け
企業はこのスケジュールを把握し、早めの準備を進める必要があります。
3.柔軟な働き方を実現するための措置
(1)始業・終業時刻の変更や短時間勤務制度の導入
柔軟な働き方を実現するためには、従業員が選択できる多様な制度を整備する必要があります。例えば、始業時刻や終業時刻を変更する制度や、短時間勤務制度を導入することが求められます。これにより、従業員は育児や介護をしながらも働きやすい環境を得られます。
(2)養育両立支援休暇とは?
この休暇は、育児と仕事の両立を支援するために導入されるもので、年に10日以上、時間単位で取得することが可能です。例えば、子どもの通院や学校行事への参加に利用できる点が特徴です。
(3)企業が取るべき対応
これらの措置を導入する際には、労働組合や従業員代表者との協議が必要です。また、制度の周知や従業員への意向確認も欠かせません。
4.所定外労働の制限と対象拡大
(1)対象者の範囲と具体的内容
今回の改正では、3歳以上小学校就学前の子どもを育てる労働者が所定外労働(残業)の制限を利用できるようになります。従業員が申請を行った場合、企業は「事業の正常な運営を妨げる場合」を除いて、この請求を受け入れる必要があります。
(2)申請手続きと事業主の対応義務
従業員は申請書を提出することで、この制限を利用できます。事業主は、申請内容を適切に審査し、必要な場合には業務の調整を行うことが求められます。
(3)運用上の注意点
申請が適切に受理されるよう、制度内容を従業員に周知し、申請プロセスを明確にすることが重要です。
5.育児・介護のためのテレワーク導入
(1)テレワークの位置づけと対象者
テレワークは、育児や介護を理由とした出社困難な従業員にとって有効な働き方です。自宅やサテライトオフィスでの業務が認められることで、時間の効率的な活用が可能になります。
(2)導入における課題と解決策
企業側の課題として、通信環境の整備や業務内容の可視化が挙げられます。この課題を克服するためには、ITツールの活用や運用ルールの明確化が必要です。
(3)中小企業での具体的な活用例
例えば、保育園の送迎時間や介護の時間帯を考慮したテレワーク制度を導入することで、従業員の負担を軽減できます。
6.子の看護休暇と介護休暇の見直し
(1)範囲拡大と新しい取得事由
改正により、子の看護休暇の対象が小学校第3学年まで拡大されました。また、新たに「感染症による学級閉鎖」や「入学式・卒業式」への参加が取得事由に追加されました。
(2)労使協定の見直しポイント
労使協定の内容が改正後の規定に適合しているかを確認し、必要に応じて修正することが重要です。
(3)労働者への周知方法
従業員への説明会や配布資料を通じて、新たな休暇制度を理解してもらう工夫が必要です。
7.個別の意向聴取と配慮
(1)意向聴取の具体的方法
事業主は、従業員の勤務時間や勤務地に関する意向を面談や書面で個別に聴取する義務があります。オンライン面談や電子メールを利用することも可能です。
(2)配慮義務の重要性
聴取した意向に基づき、業務内容や勤務条件を調整することが求められます。この配慮が従業員の満足度向上や離職防止につながります。
(3)配慮が企業に与えるメリット
従業員の仕事と家庭の両立を支援することで、職場全体のモチベーション向上や生産性向上が期待できます。
8.中小企業がとるべき具体的な対応策
(1)就業規則の改訂ポイント
改正内容を反映させるため、就業規則を見直し、必要な改訂を行う必要があります。特に、柔軟な働き方や休暇制度に関する記載を充実させましょう。
(2)労働者への制度周知と教育
新たな制度の導入に伴い、従業員への説明会や研修を実施し、理解を深めてもらうことが重要です。
(3)相談窓口の設置と活用
従業員が気軽に相談できる窓口を設けることで、制度の利用促進と問題解決を図ることができます。
9.まとめ
令和6年の改正育児・介護休業法は、企業に新たな義務を課す一方で、従業員の働きやすさを向上させ、職場環境を改善する好機でもあります。本記事で解説した内容を参考に、適切な対応を進めることで、企業としての魅力を高めましょう。当事務所では、制度導入や就業規則改訂のサポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

-
木戸社会保険労務士事務所の三代目の石田厳志と申します。当事務所は、私の祖父の初代所長木戸琢磨が昭和44年に開業し、長年に渡って企業の発展と、そしてそこで働く従業員の方々の福祉の向上を目指し、多くの皆様に支えられて社会保険労務士業を行ってまいりました。
当事務所は『労働保険・社会保険の手続』『給与計算』『就業規則の作成・労働トラブルの相談』『役所の調査への対応』『障害年金の請求』等を主たる業務としており、経営者の困り事を解決するために、日々尽力しています。経営者の方々の身近で頼れる相談相手をモットーに、きめ細かくお客様目線で真摯に対応させていただきます。
最新の投稿
 三代目のブログ2026年1月1日第8回:行動評価制度の設計 (2) – 評価要素と手続き
三代目のブログ2026年1月1日第8回:行動評価制度の設計 (2) – 評価要素と手続き 三代目のブログ2025年12月1日第7回:行動評価制度の設計 (1) – 目的と基本構造
三代目のブログ2025年12月1日第7回:行動評価制度の設計 (1) – 目的と基本構造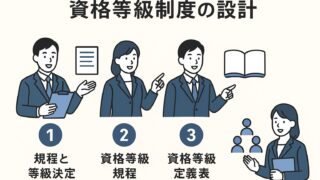 三代目のブログ2025年11月1日第6回:「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (3) ― 規程と等級決定
三代目のブログ2025年11月1日第6回:「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (3) ― 規程と等級決定 三代目のブログ2025年10月1日第5回「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (2) – 仕事しらべ
三代目のブログ2025年10月1日第5回「人を育てる人事制度」資格等級制度の設計 (2) – 仕事しらべ